医療業界転職で差がつく!個別化医療の基礎と実情
2024/05/14
2025/11/11
医療業界への転職を目指すなら、今注目されている「個別化医療」の知識は必須です。遺伝子情報を活用し、一人ひとりに最適化された治療を行うこのアプローチは、がん治療をはじめ幅広い疾患で導入が進んでいます。
本記事では、個別化医療の基本から最新の動向、転職時に役立つスキルや知識までを詳しく解説します。
本記事では、個別化医療の基本から最新の動向、転職時に役立つスキルや知識までを詳しく解説します。
個別化医療とはどんなもの?これまでの医療との違いは?
個別化医療とは、患者一人ひとりの体質や病気のタイプに合わせて治療を行うことを指します。例えば、治療前に遺伝子検査などの詳細な検査を実施し、患者の体質や病気のタイプを把握し、より安全性が高く効果的な薬を選んで処方するといった治療法です。「オーダーメイド医療」「プレシジョン・メディシン」などとも呼ばれます。
従来は、同じ病気だと診断された全ての患者に対し、共通して同じ治療を行う「標準治療」が重要視されていました。標準治療は、試験や調査をはじめとする研究結果などの科学的根拠に基づいており、多くの患者に現在できる最良の治療であると推奨される治療のことです。医療を標準化することで、多くの患者が一定レベルの治療を受けられるというメリットがあります。
しかし、標準化した医療は、膨大な検査・治療データをもとにつくられており、それぞれの患者や病気の性質や環境の違いはあまり考慮されていません。
そのため、同じ治療をしたとしても、全員が同じ経過をたどるとは限らないと判明しました。複数の同じ病気を持つ患者に同じ薬を処方しても、効果や副作用の個人差が大きく、思ったような結果が出なかったり、副作用が強すぎて服薬を中止せざるを得なかったりするケースがあります。
医学の発達により、治療の結果に関する個人差に患者の遺伝子が深く関わっているとわかってきました。
また、これまで同一の病気だと考えられていた疾患を遺伝子やタンパク質などより詳細に調べたところ、いくつかのパターンにわかれ、全く同じではないことも判明しました。
それに伴い、それぞれの患者に合った治療を行う個別化医療が求められるようになったのです。現在の個別化医療では、ある薬に対し高い効果が期待でき副作用の少ない患者を選別して、処方する治療が行われています。
従来は、同じ病気だと診断された全ての患者に対し、共通して同じ治療を行う「標準治療」が重要視されていました。標準治療は、試験や調査をはじめとする研究結果などの科学的根拠に基づいており、多くの患者に現在できる最良の治療であると推奨される治療のことです。医療を標準化することで、多くの患者が一定レベルの治療を受けられるというメリットがあります。
しかし、標準化した医療は、膨大な検査・治療データをもとにつくられており、それぞれの患者や病気の性質や環境の違いはあまり考慮されていません。
そのため、同じ治療をしたとしても、全員が同じ経過をたどるとは限らないと判明しました。複数の同じ病気を持つ患者に同じ薬を処方しても、効果や副作用の個人差が大きく、思ったような結果が出なかったり、副作用が強すぎて服薬を中止せざるを得なかったりするケースがあります。
医学の発達により、治療の結果に関する個人差に患者の遺伝子が深く関わっているとわかってきました。
また、これまで同一の病気だと考えられていた疾患を遺伝子やタンパク質などより詳細に調べたところ、いくつかのパターンにわかれ、全く同じではないことも判明しました。
それに伴い、それぞれの患者に合った治療を行う個別化医療が求められるようになったのです。現在の個別化医療では、ある薬に対し高い効果が期待でき副作用の少ない患者を選別して、処方する治療が行われています。
安全で効果的な治療ができる!個別化医療のメリットとは
患者や病気のタイプに合わせたピンポイントの治療ができる個別化医療には、多くのメリットがあります。
個別化医療の最大のメリットは、患者の体質や病気のタイプに合わせた治療をするため、高い効果が期待できる点です。
例えばがん治療の場合、患者のがん細胞が持つ特定の遺伝子変異にアプローチする治療薬を使用することで、標準治療など他の治療よりも高い効果が期待できます。
同じ医薬品を投与しても、患者の体質によって副作用の強さは異なります。場合によっては、治療が継続できないほどの深刻な副作用がでる場合があるほどです。特にがん治療では、副作用が大きな問題となるケースが少なくありません。
個別化医療によって副作用をおさえられれば、これまでは治療が難しかった患者の回復や治療の選択肢の広がりなどが期待できます。
標準治療の場合、一般的にその病気に対して効果が高いと考えられる医薬品を投与し、効果が出なければ別の医薬品を試すといったプロセスが発生します。
個別化医療の場合は、事前の検査によって効果があると判明した医薬品に絞って服用できます。無駄な医薬品を投与しない分、医療費を節約できる可能性が高いでしょう。
高い効果が期待できる医薬品をピンポイントで使用することにより、治療法を試行錯誤する時間を節約できます。標準治療よりも、効果が高い分、回復も早いと考えられます。
治療期間を短縮でき、早期に会社や学校への復帰が可能です。本人や家族などの周りでサポートする人にとって大きなメリットだといえるでしょう。
異なる病気であっても遺伝子の特徴が同じであれば、同じ医薬品が効く可能性があります。
コストや時間などの関係で病気ごとに臨床試験を実施するのは難しい場合でも、遺伝子の特徴が共通した病気の臨床試験をまとめて行うことが可能です。
その結果、スムーズに新薬の開発が進み、多くの患者の生命や健康を守れます。
(1)高い治療効果
個別化医療の最大のメリットは、患者の体質や病気のタイプに合わせた治療をするため、高い効果が期待できる点です。
例えばがん治療の場合、患者のがん細胞が持つ特定の遺伝子変異にアプローチする治療薬を使用することで、標準治療など他の治療よりも高い効果が期待できます。
(2)副作用の軽減
同じ医薬品を投与しても、患者の体質によって副作用の強さは異なります。場合によっては、治療が継続できないほどの深刻な副作用がでる場合があるほどです。特にがん治療では、副作用が大きな問題となるケースが少なくありません。
個別化医療によって副作用をおさえられれば、これまでは治療が難しかった患者の回復や治療の選択肢の広がりなどが期待できます。
(3)医療費の抑制
標準治療の場合、一般的にその病気に対して効果が高いと考えられる医薬品を投与し、効果が出なければ別の医薬品を試すといったプロセスが発生します。
個別化医療の場合は、事前の検査によって効果があると判明した医薬品に絞って服用できます。無駄な医薬品を投与しない分、医療費を節約できる可能性が高いでしょう。
(4)治療期間の短縮
高い効果が期待できる医薬品をピンポイントで使用することにより、治療法を試行錯誤する時間を節約できます。標準治療よりも、効果が高い分、回復も早いと考えられます。
治療期間を短縮でき、早期に会社や学校への復帰が可能です。本人や家族などの周りでサポートする人にとって大きなメリットだといえるでしょう。
(5)新薬開発の効率化
異なる病気であっても遺伝子の特徴が同じであれば、同じ医薬品が効く可能性があります。
コストや時間などの関係で病気ごとに臨床試験を実施するのは難しい場合でも、遺伝子の特徴が共通した病気の臨床試験をまとめて行うことが可能です。
その結果、スムーズに新薬の開発が進み、多くの患者の生命や健康を守れます。
リソースが足りない?個別化医療の課題とは
高い効果と安全性などメリットの多い個別化医療ですが、新しい分野ということもあり課題も多いのが現状です。主な課題について解説します。
個別化医療を実施するには、従来の標準医療とは異なる検査方法や治療薬を使用します。そのため、実施できる設備や専門知識・技術を持つ人材が不足しています。多額のコストや人的リソースが必要なため、医療機関によってはすぐに取り入れるのは難しいのが現状です。
また、遺伝子検査をした結果、患者の遺伝情報や病気のタイプがわかっても、対応できる治療薬がないケースがあります。
今のところ個別化医療は主にがん治療を対象としていますが、今後は呼吸器系や神経系の病気にも広く使われるようになると予想されているため、リソース不足は大きな課題です。
個別化医療においては、適切な検査や検査の読み解きが非常に重要です。遺伝子検査はまだ新しい分野なので、品質・精度を担保するための基準を決める、検査結果の読み解き方法を検討するなどの取り組みが不可欠です。
遺伝子検査を実施した結果、予期せぬ治療法が確立していない病気のリスクが判明する、遺伝性の病気の検査結果が家族に影響を与えるといった場合もあります。
患者本人が、検査結果をもとにしたどうするべきかを悩む可能性も高く、カウンセリングなど手厚くサポートする必要があるでしょう。
本人や家族にとって遺伝情報は、重要な個人情報です。病気や体質に関する情報を含むため、万が一漏えいした場合は、精神的なダメージや差別のリスクなど重大な被害が発生するでしょう。
漏えいしないよう、遺伝情報を取り扱う医療機関などのセキュリティの構築や、データを適性に取り扱う専門職の育成などに取り組む必要があります。
就職や結婚、保険の加入などの際に、特定の病気が起きる因子を持っているといった遺伝情報によって、差別にあう可能性があります。
すでにアメリカでは、発症していない、または治療によって健康である人に対しても、遺伝子情報だけで差別が起きているケースもあります。
アメリカやドイツなどでは差別禁止法が制定されており、日本でも差別を防ぐために法整備などの対策が必要です。
(1)リソース不足
個別化医療を実施するには、従来の標準医療とは異なる検査方法や治療薬を使用します。そのため、実施できる設備や専門知識・技術を持つ人材が不足しています。多額のコストや人的リソースが必要なため、医療機関によってはすぐに取り入れるのは難しいのが現状です。
また、遺伝子検査をした結果、患者の遺伝情報や病気のタイプがわかっても、対応できる治療薬がないケースがあります。
今のところ個別化医療は主にがん治療を対象としていますが、今後は呼吸器系や神経系の病気にも広く使われるようになると予想されているため、リソース不足は大きな課題です。
(2)品質の保証
個別化医療においては、適切な検査や検査の読み解きが非常に重要です。遺伝子検査はまだ新しい分野なので、品質・精度を担保するための基準を決める、検査結果の読み解き方法を検討するなどの取り組みが不可欠です。
(3)検査結果に対してのフォロー
遺伝子検査を実施した結果、予期せぬ治療法が確立していない病気のリスクが判明する、遺伝性の病気の検査結果が家族に影響を与えるといった場合もあります。
患者本人が、検査結果をもとにしたどうするべきかを悩む可能性も高く、カウンセリングなど手厚くサポートする必要があるでしょう。
(4)個人情報保護の徹底
本人や家族にとって遺伝情報は、重要な個人情報です。病気や体質に関する情報を含むため、万が一漏えいした場合は、精神的なダメージや差別のリスクなど重大な被害が発生するでしょう。
漏えいしないよう、遺伝情報を取り扱う医療機関などのセキュリティの構築や、データを適性に取り扱う専門職の育成などに取り組む必要があります。
(5)差別の原因になる可能性
就職や結婚、保険の加入などの際に、特定の病気が起きる因子を持っているといった遺伝情報によって、差別にあう可能性があります。
すでにアメリカでは、発症していない、または治療によって健康である人に対しても、遺伝子情報だけで差別が起きているケースもあります。
アメリカやドイツなどでは差別禁止法が制定されており、日本でも差別を防ぐために法整備などの対策が必要です。
日本における個別化医療の最新動向とデータ活用の現状
ゲノム情報を活用した医療体制の整備
近年、日本においても個別化医療をめぐる取り組みが本格化しています。特に注目されているのが、ゲノム情報を活用した医療体制の整備や、医療DXの推進によるデータ活用の加速です。
たとえば、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)では、約36.6万人規模のゲノムコホートが構築されており、さまざまな疾患の発症リスクの予測や、最適な治療法の確立に活用されています。
出典:国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)
医療DXによる診療データの活用
また、政府が進める医療DXでは、全国の医療機関が保有する診療データの標準化と共有化が進められており、個別化医療の精度向上や新薬開発の効率化にも貢献しています。
出典:首相官邸(健康・医療戦略推進本部 資料)
今後の展望と応用の広がり
このように、データの利活用が進むことで、がんだけでなく心疾患、糖尿病、神経疾患など幅広い領域での応用が期待されており、今後ますます注目が集まる分野といえるでしょう。
医療業界で求められるスキルと個別化医療への対応
注目されるスキルセットと背景
個別化医療の拡大に伴い、医療業界で働く人に求められるスキルも変化しています。中でも重要なのが、遺伝情報の取り扱いやデータ解析の基礎知識です。
コミュニケーション力と教育の充実
たとえば、遺伝子検査の結果を適切に理解し、治療方針に反映できる能力や、患者や家族に対してわかりやすく説明できるコミュニケーション力が求められます。また、大学や医療機関では、医療従事者向けにゲノム医療や個別化医療に関する教育プログラムの提供も始まっており、専門知識を持った人材の育成が進んでいます。
転職市場での活かし方
実際に、看護師や臨床検査技師などが関連する資格取得を目指すケースも増えており、転職を検討する際には、こうしたスキルを身につけておくことで、専門性の高い分野へのキャリアアップが期待できます。
個別化医療は今後ますます広がる分野であり、それに対応できる人材の需要も高まっています。医療業界への転職を考えている方は、ぜひこうした新しい医療のあり方に目を向けてみてください。
まとめ
個別化医療とは、治療をスタートする前に遺伝子検査などを行い、患者の体質や病気のタイプを細かく調べたうえで、最適な治療法を選ぶ方法です。主にがん治療において、効果が高く副作用の少ない医薬品を見つけるために行われています。
従来の標準医療では、同じ病気の患者には基本的に同じ治療をしていましたが、効果が上がらなかったり副作用が強かったりといった課題があります。個別化医療は、その解決策として広がりつつある手法です。
高い治療効果に加え、副作用の軽減・医療費の抑制・治療期間の短縮など多くのメリットがあります。その反面、リソース不足・品質の保証・検査結果に対してのフォローなどの課題もあります。
今後は呼吸器系などがん以外の病気の治療にも普及すると考えられています。医療業界への転職を考えている方は、個別化医療の話題にアンテナを張っておきましょう。
従来の標準医療では、同じ病気の患者には基本的に同じ治療をしていましたが、効果が上がらなかったり副作用が強かったりといった課題があります。個別化医療は、その解決策として広がりつつある手法です。
高い治療効果に加え、副作用の軽減・医療費の抑制・治療期間の短縮など多くのメリットがあります。その反面、リソース不足・品質の保証・検査結果に対してのフォローなどの課題もあります。
今後は呼吸器系などがん以外の病気の治療にも普及すると考えられています。医療業界への転職を考えている方は、個別化医療の話題にアンテナを張っておきましょう。
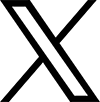
この記事が気に入った場合は
Xへポストをお願いします
