予防医療×デジタルとは?健康寿命を延ばす最新技術と具体事例を解説
2023/03/14
2025/11/28
生活習慣病や認知症など、長く付き合う病気が増えるなかで、「予防医療」と「デジタル技術」を組み合わせた取り組みが注目されています。日本は65歳以上人口が全体の29%を超える超高齢社会であり、医療費・介護費の増加や医療人材不足が大きな課題になっています。
さらに、2022年時点の平均寿命は男性81.05歳・女性87.09歳であるのに対し、健康寿命は男性72.57歳・女性75.45歳と、日常生活に制限のある期間が男性で約8.5年、女性で約11.6年生じていることも分かっています。 この「寿命と健康寿命のギャップ」を縮めるために、病気になる前から生活習慣を整え、発症や重症化を防ぐ予防医療がこれまで以上に重要になっています。
一方で、日本では高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病で治療を受けている人が数千万人規模にのぼり、日々の生活に根ざした継続的な支援なしには予防の徹底が難しいのも現実です。 そこで期待されているのが、アプリやウェアラブルデバイス、オンライン保健指導、AIによるリスク予測など、デジタル技術を活用した「予防医療×デジタル」の取り組みです。
厚生労働省が進める医療DXやデータヘルス計画とも連動しながら、個人・企業・医療機関を巻き込んだ新しい予防モデルが広がりつつあります。
本記事では、予防医療の基本的な考え方やデジタル技術が果たす役割、日本で進む具体的なサービス・事例、そしてこの分野に関わる仕事・キャリアの可能性までを分かりやすく解説します。
さらに、2022年時点の平均寿命は男性81.05歳・女性87.09歳であるのに対し、健康寿命は男性72.57歳・女性75.45歳と、日常生活に制限のある期間が男性で約8.5年、女性で約11.6年生じていることも分かっています。 この「寿命と健康寿命のギャップ」を縮めるために、病気になる前から生活習慣を整え、発症や重症化を防ぐ予防医療がこれまで以上に重要になっています。
一方で、日本では高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病で治療を受けている人が数千万人規模にのぼり、日々の生活に根ざした継続的な支援なしには予防の徹底が難しいのも現実です。 そこで期待されているのが、アプリやウェアラブルデバイス、オンライン保健指導、AIによるリスク予測など、デジタル技術を活用した「予防医療×デジタル」の取り組みです。
厚生労働省が進める医療DXやデータヘルス計画とも連動しながら、個人・企業・医療機関を巻き込んだ新しい予防モデルが広がりつつあります。
本記事では、予防医療の基本的な考え方やデジタル技術が果たす役割、日本で進む具体的なサービス・事例、そしてこの分野に関わる仕事・キャリアの可能性までを分かりやすく解説します。
デジタル技術で病気を防ぐ!最先端の予防医療とは
ここでは、デジタルヘルスケアと予防治療の基本的な知識を解説します。
「ヘルスケア」とは、健康の維持・向上のためにする行動や健康管理を意味します。デジタルヘルスケアは、デジタル技術を活用してヘルスケアを行うことを指します。
デジタルヘルスケアで用いられる主なデジタル技術は、人工知能(AI)やチャットボット、ウェアラブルデバイス、ビッグデータ解析などさまざまです。
デジタル技術の活用により、血圧といった身体の状態や人の行動といったデータを効率的に収集できるようになり、科学的なデータを根拠とした健康管理や病気の予防が可能になります。
また、チャットボットなどの導入により、医師をはじめとする専門家にアクセスしやすくなるのもデジタルヘルスケアの大きなメリットです。
予防医療とは、病気になってから治療するのではなく、病気にならないよう健康な状態をできるだけ長く維持することを指します。
デジタルヘルスケアを活用した予防医療では、下記のようなアプローチをしています。
●スマートフォンアプリなどの情報提供の場を設け、患者に必要な予防・治療にアクセスできる環境を整える
●身体の状態や日々の行動といったデータをもとに、医学的な見地から行動の変化につながるアドバイスをする
デジタルヘルスケアを活用した予防医療は、幅広い病気に活用されていますが、特に高血圧や糖尿病といった生活習慣病に効果を発揮する方法です。血圧などのデータから注意喚起したり、栄養バランスのとれた食生活や適度な運動を促したりすることで、生活習慣病のリスクを軽減できます。
デジタルヘルスケアが登場する前から、病気の予防には生活習慣の改善が有効なのは広く知られています。しかし、病気にかかる前に、日々の生活を変えるのは難しいといえるでしょう。自覚症状がないまま進行し、発症すると健康を大きく損ねたり、高額の医療費がかかったりといったリスクが考えられます。
予防医療は、一般的に「一次予防」「二次予防」「三次予防」の3つに分けられます。
一次予防:病気を発症する前にリスク要因を減らし、発症を防ぐ段階(生活習慣の改善など)
二次予防:検診や検査で病気をできるだけ早く見つけ、早期治療につなげる段階
三次予防:再発・重症化・合併症を防ぎ、症状のコントロールやQOL維持をめざす段階
デジタル技術は、この3つの段階すべてで活用されています。たとえば一次予防では、アプリやウェアラブルデバイスで歩数・睡眠・食事などの日々のデータを可視化し、行動変容プログラムと組み合わせることで生活習慣の改善を促します。二次予防では、健診データや画像診断データをAIで解析し、将来の発症リスクが高い人を早期に抽出する取り組みが進んでいます。三次予防では、慢性疾患患者の血圧・血糖・体重などを在宅でモニタリングし、アプリやオンライン面談を通じて医療者から継続的なフォローを受けられる仕組みが整いつつあります。
このように、デジタル技術を組み合わせることで、予防医療を「一度きりの指導」から「データに基づく継続的な支援」に変えていける点が大きな特徴です。
デジタル技術の活用により、その人の志向やライフスタイルに合わせた行動変容プログラムを提供し、経過をチェックできるようになるため、生活改善のハードルは大幅に下がるはずです。
(1)デジタルヘルスケアとは
「ヘルスケア」とは、健康の維持・向上のためにする行動や健康管理を意味します。デジタルヘルスケアは、デジタル技術を活用してヘルスケアを行うことを指します。
デジタルヘルスケアで用いられる主なデジタル技術は、人工知能(AI)やチャットボット、ウェアラブルデバイス、ビッグデータ解析などさまざまです。
デジタル技術の活用により、血圧といった身体の状態や人の行動といったデータを効率的に収集できるようになり、科学的なデータを根拠とした健康管理や病気の予防が可能になります。
また、チャットボットなどの導入により、医師をはじめとする専門家にアクセスしやすくなるのもデジタルヘルスケアの大きなメリットです。
(2)デジタルヘルスケアを活用した予防医療とは
予防医療とは、病気になってから治療するのではなく、病気にならないよう健康な状態をできるだけ長く維持することを指します。
デジタルヘルスケアを活用した予防医療では、下記のようなアプローチをしています。
●スマートフォンアプリなどの情報提供の場を設け、患者に必要な予防・治療にアクセスできる環境を整える
●身体の状態や日々の行動といったデータをもとに、医学的な見地から行動の変化につながるアドバイスをする
デジタルヘルスケアを活用した予防医療は、幅広い病気に活用されていますが、特に高血圧や糖尿病といった生活習慣病に効果を発揮する方法です。血圧などのデータから注意喚起したり、栄養バランスのとれた食生活や適度な運動を促したりすることで、生活習慣病のリスクを軽減できます。
デジタルヘルスケアが登場する前から、病気の予防には生活習慣の改善が有効なのは広く知られています。しかし、病気にかかる前に、日々の生活を変えるのは難しいといえるでしょう。自覚症状がないまま進行し、発症すると健康を大きく損ねたり、高額の医療費がかかったりといったリスクが考えられます。
(3)予防医療の3つの段階とデジタル技術の役割
予防医療は、一般的に「一次予防」「二次予防」「三次予防」の3つに分けられます。
一次予防:病気を発症する前にリスク要因を減らし、発症を防ぐ段階(生活習慣の改善など)
二次予防:検診や検査で病気をできるだけ早く見つけ、早期治療につなげる段階
三次予防:再発・重症化・合併症を防ぎ、症状のコントロールやQOL維持をめざす段階
デジタル技術は、この3つの段階すべてで活用されています。たとえば一次予防では、アプリやウェアラブルデバイスで歩数・睡眠・食事などの日々のデータを可視化し、行動変容プログラムと組み合わせることで生活習慣の改善を促します。二次予防では、健診データや画像診断データをAIで解析し、将来の発症リスクが高い人を早期に抽出する取り組みが進んでいます。三次予防では、慢性疾患患者の血圧・血糖・体重などを在宅でモニタリングし、アプリやオンライン面談を通じて医療者から継続的なフォローを受けられる仕組みが整いつつあります。
このように、デジタル技術を組み合わせることで、予防医療を「一度きりの指導」から「データに基づく継続的な支援」に変えていける点が大きな特徴です。
デジタル技術の活用により、その人の志向やライフスタイルに合わせた行動変容プログラムを提供し、経過をチェックできるようになるため、生活改善のハードルは大幅に下がるはずです。
なぜ必要?デジタル技術を活用した予防医療が注目される背景とは
近年、デジタル技術を活用した予防医療が注目されているのには下記のような背景があります。
日本は、65歳以上人口が総人口の29.1%(令和5年10月1日現在)を占める世界有数の高齢社会です。一般に、65歳以上人口が21%以上の社会は「超高齢社会」と定義されますが、日本はこの水準を大きく上回っています。
高齢者が増えると、生活習慣病や要介護状態など長期の医療・介護を必要とする人が増加し、医療費や介護費の負担が重くなります。また、現役世代(15〜64歳人口)が減るなかで、1人の高齢者を支える現役世代の人数は令和5年には2.0人まで低下しており、社会保障制度の持続可能性も大きな課題です。
デジタル技術を活用した予防医療により、病気の発症や重症化を防ぐことができれば、医療費・介護費の抑制や医療・介護人材の負担軽減につながると期待されています。
かつて日本人がかかる病気は、結核や肺炎といった感染症など、急激に発症する「急性疾患」が主でした。しかし、医学の発達や生活スタイルの欧米化に伴い、がん・心臓病などの循環器疾患・糖尿病などの生活習慣病といった「慢性疾患」にかかる人の割合が増加しています。それに伴い、予防医療の重要性が高まっています。
慢性疾患は、少しずつ発症し治療が長期化する疾患です。そのため、予防医療を行えば、発症を未然に防げる、発症しても軽症で済むといったケースも少なくありません。また、慢性疾患の多くは、生活習慣との関係が深いため、予防医療による効果が高いと考えられます。
デジタル技術の活用により、生活改善に必要なデータ収集や指導が容易になれば、効果的に予防できるでしょう。
近年公表された令和5年(2023年)「患者調査」によると、高血圧性疾患で治療を受けている総患者数は約1,609万人、糖尿病は約552万人、脂質異常症は約459万人とされています。いずれも前回調査(令和2年)から増加しており、日本では生活習慣病が身近で長期の治療を要する「国民病」となっていることが分かります。
こうした疾患は食事・運動・睡眠・喫煙など日々の生活習慣と深く結びついているため、日常生活に密着したデジタル技術を組み合わせることで、発症予防や重症化予防の効果が期待されています。
「健康寿命」とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間を指します。
厚生労働省のまとめによると、2022年時点での日本人の平均寿命は、男性が81.05歳、女性が87.09歳です。一方、同年の健康寿命は男性が72.57歳、女性が75.45歳とされており、平均寿命との差はそれぞれ約8.5年、約11.6年あります。つまり、この期間は日常生活に何らかの制限がある「不健康な期間」であると考えられます。
平均寿命が延びること自体は望ましいものの、健康寿命とのギャップが大きい状態は、本人の生活の質(QOL)だけでなく、医療費・介護費の増大という面でも大きな課題です。デジタル技術を活用した予防医療で生活習慣を改善し、健康状態を継続的にモニタリングすることは、このギャップを縮めるうえで重要なアプローチといえます。
なお、国の「健康日本21」や「健康寿命延伸プラン」では、2040年までに健康寿命を男女ともに3年以上延ばし、75歳以上を目指すという目標が掲げられており、予防医療の推進とデジタル技術の活用は、その実現に向けた重要な柱の一つと位置づけられています。
厚生労働省は、「医療DX」の一環として、疾病の発症予防から診療、介護までの各場面でデータを活用し、一人ひとりに最適な医療・健康づくりを提供する仕組みづくりを進めています。
また、医療保険者(健保・国保など)がレセプトや健診データを分析し、生活習慣病の発症予防・重症化予防に取り組む「データヘルス計画」も、第3期に向けて見直し・強化が進められています。
こうした国の政策の流れからも、デジタル技術を活用した予防医療は、一時的なブームではなく、中長期的に重視される領域であることが分かります。
(1)超高齢化社会
日本は、65歳以上人口が総人口の29.1%(令和5年10月1日現在)を占める世界有数の高齢社会です。一般に、65歳以上人口が21%以上の社会は「超高齢社会」と定義されますが、日本はこの水準を大きく上回っています。
高齢者が増えると、生活習慣病や要介護状態など長期の医療・介護を必要とする人が増加し、医療費や介護費の負担が重くなります。また、現役世代(15〜64歳人口)が減るなかで、1人の高齢者を支える現役世代の人数は令和5年には2.0人まで低下しており、社会保障制度の持続可能性も大きな課題です。
デジタル技術を活用した予防医療により、病気の発症や重症化を防ぐことができれば、医療費・介護費の抑制や医療・介護人材の負担軽減につながると期待されています。
(2)慢性疾患へのシフト
かつて日本人がかかる病気は、結核や肺炎といった感染症など、急激に発症する「急性疾患」が主でした。しかし、医学の発達や生活スタイルの欧米化に伴い、がん・心臓病などの循環器疾患・糖尿病などの生活習慣病といった「慢性疾患」にかかる人の割合が増加しています。それに伴い、予防医療の重要性が高まっています。
慢性疾患は、少しずつ発症し治療が長期化する疾患です。そのため、予防医療を行えば、発症を未然に防げる、発症しても軽症で済むといったケースも少なくありません。また、慢性疾患の多くは、生活習慣との関係が深いため、予防医療による効果が高いと考えられます。
デジタル技術の活用により、生活改善に必要なデータ収集や指導が容易になれば、効果的に予防できるでしょう。
近年公表された令和5年(2023年)「患者調査」によると、高血圧性疾患で治療を受けている総患者数は約1,609万人、糖尿病は約552万人、脂質異常症は約459万人とされています。いずれも前回調査(令和2年)から増加しており、日本では生活習慣病が身近で長期の治療を要する「国民病」となっていることが分かります。
こうした疾患は食事・運動・睡眠・喫煙など日々の生活習慣と深く結びついているため、日常生活に密着したデジタル技術を組み合わせることで、発症予防や重症化予防の効果が期待されています。
(3)平均寿命と健康寿命のギャップ
「健康寿命」とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間を指します。
厚生労働省のまとめによると、2022年時点での日本人の平均寿命は、男性が81.05歳、女性が87.09歳です。一方、同年の健康寿命は男性が72.57歳、女性が75.45歳とされており、平均寿命との差はそれぞれ約8.5年、約11.6年あります。つまり、この期間は日常生活に何らかの制限がある「不健康な期間」であると考えられます。
平均寿命が延びること自体は望ましいものの、健康寿命とのギャップが大きい状態は、本人の生活の質(QOL)だけでなく、医療費・介護費の増大という面でも大きな課題です。デジタル技術を活用した予防医療で生活習慣を改善し、健康状態を継続的にモニタリングすることは、このギャップを縮めるうえで重要なアプローチといえます。
なお、国の「健康日本21」や「健康寿命延伸プラン」では、2040年までに健康寿命を男女ともに3年以上延ばし、75歳以上を目指すという目標が掲げられており、予防医療の推進とデジタル技術の活用は、その実現に向けた重要な柱の一つと位置づけられています。
(4)医療DX・データヘルス計画による予防・重症化予防の推進
厚生労働省は、「医療DX」の一環として、疾病の発症予防から診療、介護までの各場面でデータを活用し、一人ひとりに最適な医療・健康づくりを提供する仕組みづくりを進めています。
また、医療保険者(健保・国保など)がレセプトや健診データを分析し、生活習慣病の発症予防・重症化予防に取り組む「データヘルス計画」も、第3期に向けて見直し・強化が進められています。
こうした国の政策の流れからも、デジタル技術を活用した予防医療は、一時的なブームではなく、中長期的に重視される領域であることが分かります。
デジタル技術を活用した予防医療はここまで来ている!事例紹介
デジタル技術を活用した予防医療サービスは、すでに数多くリリースされています。代表的な事例を紹介します。
デジタル技術を活用した予防医療サービスは、大きく次のようなタイプに分けられます。
個人向け(BtoC)サービス:健康管理アプリやウェアラブルデバイスを用いて、歩数・睡眠・食事・体重などを可視化し、行動変容を支援するタイプ
保険者・企業による健康支援(BtoBtoC)サービス:健康保険組合や自治体、企業が加入者・従業員に対して提供するオンライン特定保健指導、生活習慣病予防プログラムなど
医療機関発のサービス:生活習慣病患者や慢性疾患患者を対象に、在宅でのバイタル計測や血糖値測定などを行い、遠隔モニタリングやオンライン指導につなげるタイプ
このあと紹介する各事例も、これらのタイプのいずれかに位置づけられます。自分がどの領域・どの立場で関わりたいのかをイメージしながら読むと、キャリアの整理にも役立つでしょう。
「HEA LTHY LAB」は、「手の中に収まる“かかりつけ医”」をコンセプトに開発されたスマートフォン向け健康管理アプリです。
スマートフォンと連携し、歩数・消費カロリー・心拍数・食事などを記録・分析することで、「健康年齢」「病気発症予測」「リスク軽減予測」を算出できます。
さらに、管理栄養士とチャットでやりとりし、自分に合ったアドバイスや健康相談を受け、改善に役立てられるメリットもあります。
身体 の状態をさまざまな機器・ツールで測定し、改善に役立てる糖尿病予備軍向けプログラムです。本人が数値をもとに体調を管理するのと並行し、日本生命病院の保健師などが遠隔で生活改善を指導します。
自分で身体の状態を把握できるので生活改善への意識が高まる、専門家の指導により具体的な行動改善につながるといったメリットがあります。
東芝グループとSOMPOホールディングスグループが共同開発した「生活習慣病リスク予測A」は、6種類の生活習慣病リスクを6年先まで予測できるAIです。
1年分の健康診断のデータから、糖尿病・高血圧症・肥満症・脂質異常症・肝機能障害・腎機能障害のリスクを算出します。糖尿病発症リスクの予測を調べたところ、90%以上の高精度でした。
デジタル技術を活用した予防医療の効果については、近年、国内外で多くの研究が行われています。たとえば、糖尿病や糖尿病予備群の人を対象に、スマートフォンアプリと行動変容プログラムを組み合わせた介入を行った研究では、血糖コントロールの指標であるHbA1cの改善や体重減少が報告されています。
海外のシステマティックレビュー・メタ分析では、モバイルアプリなどのモバイルヘルス(mHealth)介入が、従来の診療のみの場合と比べて、HbA1cを平均0.3〜0.4%程度改善させたとする報告もあります。一方で、長期的なフォローアップでは、体重や血糖コントロールへの影響が小さくなるとする研究もあり、効果を維持するための仕組みづくりが今後の課題とされています。
日本でも、持続血糖測定(CGM)とスマホアプリを組み合わせた生活習慣改善プログラムを用い、高リスクの2型糖尿病予備群に介入したランダム化比較試験で、血糖の変動や体重が改善したという報告が出ています。こうした研究から、デジタル技術を活用した予防医療は、適切に設計・運用すれば、生活習慣病の予防や重症化予防に一定の効果が期待できると考えられています。
デジタル予防医療サービスの主なタイプ
デジタル技術を活用した予防医療サービスは、大きく次のようなタイプに分けられます。
個人向け(BtoC)サービス:健康管理アプリやウェアラブルデバイスを用いて、歩数・睡眠・食事・体重などを可視化し、行動変容を支援するタイプ
保険者・企業による健康支援(BtoBtoC)サービス:健康保険組合や自治体、企業が加入者・従業員に対して提供するオンライン特定保健指導、生活習慣病予防プログラムなど
医療機関発のサービス:生活習慣病患者や慢性疾患患者を対象に、在宅でのバイタル計測や血糖値測定などを行い、遠隔モニタリングやオンライン指導につなげるタイプ
このあと紹介する各事例も、これらのタイプのいずれかに位置づけられます。自分がどの領域・どの立場で関わりたいのかをイメージしながら読むと、キャリアの整理にも役立つでしょう。
(1)HEALTHY LAB:株式会社M-aid
「HEA LTHY LAB」は、「手の中に収まる“かかりつけ医”」をコンセプトに開発されたスマートフォン向け健康管理アプリです。
スマートフォンと連携し、歩数・消費カロリー・心拍数・食事などを記録・分析することで、「健康年齢」「病気発症予測」「リスク軽減予測」を算出できます。
さらに、管理栄養士とチャットでやりとりし、自分に合ったアドバイスや健康相談を受け、改善に役立てられるメリットもあります。
(2)糖尿病予防プログラム:日本生命保険相互会社
身体 の状態をさまざまな機器・ツールで測定し、改善に役立てる糖尿病予備軍向けプログラムです。本人が数値をもとに体調を管理するのと並行し、日本生命病院の保健師などが遠隔で生活改善を指導します。
自分で身体の状態を把握できるので生活改善への意識が高まる、専門家の指導により具体的な行動改善につながるといったメリットがあります。
(3)生活習慣病リスク予測AI :東芝デジタルソリューションズ株式会社
東芝グループとSOMPOホールディングスグループが共同開発した「生活習慣病リスク予測A」は、6種類の生活習慣病リスクを6年先まで予測できるAIです。
1年分の健康診断のデータから、糖尿病・高血圧症・肥満症・脂質異常症・肝機能障害・腎機能障害のリスクを算出します。糖尿病発症リスクの予測を調べたところ、90%以上の高精度でした。
デジタル予防医療の効果は?研究で報告されている成果
デジタル技術を活用した予防医療の効果については、近年、国内外で多くの研究が行われています。たとえば、糖尿病や糖尿病予備群の人を対象に、スマートフォンアプリと行動変容プログラムを組み合わせた介入を行った研究では、血糖コントロールの指標であるHbA1cの改善や体重減少が報告されています。
海外のシステマティックレビュー・メタ分析では、モバイルアプリなどのモバイルヘルス(mHealth)介入が、従来の診療のみの場合と比べて、HbA1cを平均0.3〜0.4%程度改善させたとする報告もあります。一方で、長期的なフォローアップでは、体重や血糖コントロールへの影響が小さくなるとする研究もあり、効果を維持するための仕組みづくりが今後の課題とされています。
日本でも、持続血糖測定(CGM)とスマホアプリを組み合わせた生活習慣改善プログラムを用い、高リスクの2型糖尿病予備群に介入したランダム化比較試験で、血糖の変動や体重が改善したという報告が出ています。こうした研究から、デジタル技術を活用した予防医療は、適切に設計・運用すれば、生活習慣病の予防や重症化予防に一定の効果が期待できると考えられています。
デジタル予防医療の課題と今後のポイント
(1)個人情報保護・セキュリティへの配慮
予防医療の分野で扱うデータは、健康状態や病歴、生活習慣など、個人のプライバシー性が高い情報が中心です。
近年、国内外で個人情報の漏えい事案が増加しており、医療・健康分野のデータ利活用においても、適切な同意取得やアクセス制御、暗号化などのセキュリティ対策が重要視されています。
事業者には、個人情報保護法や各種ガイドラインに沿った運用が求められ、利用者側も「どのようなデータが、どの目的で使われるのか」を理解したうえでサービスを選ぶことが大切です。
(2)高齢者を中心としたデジタルデバイド
スマートフォンやアプリを前提としたサービスが増える一方で、高齢者を中心に「デジタル機器の操作に不安がある」「オンラインサービスの存在自体を知らない」といったデジタルデバイド(情報格差)が課題となっています。
総務省などによるデジタル活用支援事業や、自治体・携帯ショップ等でのスマホ講習会など、支援の取り組みも始まっていますが、予防医療サービス側も、操作をシンプルにする、紙や電話との併用を用意するなど、高齢者にも使いやすい設計が求められます。
(3)効果エビデンスの蓄積と継続利用の仕組み
短期的には血糖値や体重、血圧などが改善したとする研究結果がある一方で、「どのくらいの期間、どの程度の行動変容が続くのか」「長期的な発症予防や医療費抑制につながるのか」といった点については、まだ十分なエビデンスが蓄積されているとは言えません。
また、健康管理アプリは数カ月で利用が途切れてしまうケースも多く、ゲーム性やコミュニティ機能、報酬設計などを通じて、利用者のモチベーションを長く維持する工夫が今後の重要なテーマです。
こうした課題を一つひとつ乗り越えながら、医療機関・企業・行政が連携してエビデンスを蓄積していくことで、デジタル技術を活用した予防医療は、より信頼性の高いインフラへと成長していくと考えられます。
予防医療×デジタルに関わる仕事・キャリアの例
予防医療とデジタル技術の組み合わせは、医療機関だけでなく、さまざまな業界・職種でキャリアの選択肢を広げています。代表的な業界・職種の一例は次のとおりです。
「臨床の現場経験を活かしつつ、新しい予防医療やデジタルヘルスにチャレンジしたい」「生活習慣病や健康経営の領域でキャリアの幅を広げたい」といった方にとって、予防医療×デジタルの領域は今後ますますチャンスが増えていくと考えられます。
(1)関わる業界の例
- 医療機器メーカー:ウェアラブルデバイスや遠隔モニタリング機器などの企画・開発・営業
- 製薬企業:生活習慣病領域などで、アプリやオンライン指導を組み合わせた「治療支援・予防プログラム」の企画
- 生命保険会社・損害保険会社:加入者向け健康増進アプリやオンライン保健指導サービスの企画・運営
- 医療系・ヘルステック系スタートアップ:デジタル予防医療サービスのプロダクトマネジメントやカスタマーサクセス
- ITベンダー・コンサルティングファーム:医療DXやデータヘルス計画に関するシステム導入支援・データ分析
(2)想定される職種の例
- 医療機器・製薬・保険会社などの営業(医療機関・企業・保険者向け)
- マーケティングやプロダクトマネージャーとして、アプリ・サービスの企画・改善を行うポジション
- 医療データアナリストとして、健診データやレセプトデータをもとにリスク分析や効果検証を行うポジション
- 保健師・管理栄養士・看護師などが、オンラインでの保健指導や生活習慣改善プログラムを提供するポジション
「臨床の現場経験を活かしつつ、新しい予防医療やデジタルヘルスにチャレンジしたい」「生活習慣病や健康経営の領域でキャリアの幅を広げたい」といった方にとって、予防医療×デジタルの領域は今後ますますチャンスが増えていくと考えられます。
まとめ
予防医療は、病気の発症を防ぐ「一次予防」、早期発見・早期治療につなげる「二次予防」、重症化や再発を防ぐ「三次予防」の3段階から成り立っており、いずれの段階でもデジタル技術の活用が進んでいます。アプリやウェアラブルで日々の生活データを見える化し、オンラインで専門職が継続的にサポートする仕組みは、従来の「一度きりの対面指導」では難しかった行動変容を後押しする手段として注目されています。
日本では、高齢化の進行や生活習慣病の増加、平均寿命と健康寿命のギャップ拡大といった課題に対し、「健康日本21」や健康寿命延伸プラン、医療DX、データヘルス計画など、国の政策としても予防・重症化予防とデータ活用の強化が打ち出されています。 デジタル技術を活用した予防医療は、こうした流れの中で、中長期的に重視される領域だと言えるでしょう。
一方で、個人情報保護やセキュリティ、デジタル機器に不慣れな人への配慮、長期的な効果エビデンスの蓄積など、解決すべき課題も少なくありません。 それでも、医療機関・企業・行政が連携してサービス設計や評価を重ねていくことで、「予防医療×デジタル」は、健康寿命の延伸と医療・介護負担の軽減を支える重要なインフラへと育っていくはずです。
医療・ヘルスケア業界でキャリアを築きたい方にとっても、予防医療とデジタル技術の知識は今後ますます求められていきます。自分の経験が活かせる領域や役割をイメージしながら、最新の動向や実例に触れていくことで、「人の健康を支えるデジタル予防医療」という新しいキャリアの選択肢が見えてくるはずです。
日本では、高齢化の進行や生活習慣病の増加、平均寿命と健康寿命のギャップ拡大といった課題に対し、「健康日本21」や健康寿命延伸プラン、医療DX、データヘルス計画など、国の政策としても予防・重症化予防とデータ活用の強化が打ち出されています。 デジタル技術を活用した予防医療は、こうした流れの中で、中長期的に重視される領域だと言えるでしょう。
一方で、個人情報保護やセキュリティ、デジタル機器に不慣れな人への配慮、長期的な効果エビデンスの蓄積など、解決すべき課題も少なくありません。 それでも、医療機関・企業・行政が連携してサービス設計や評価を重ねていくことで、「予防医療×デジタル」は、健康寿命の延伸と医療・介護負担の軽減を支える重要なインフラへと育っていくはずです。
医療・ヘルスケア業界でキャリアを築きたい方にとっても、予防医療とデジタル技術の知識は今後ますます求められていきます。自分の経験が活かせる領域や役割をイメージしながら、最新の動向や実例に触れていくことで、「人の健康を支えるデジタル予防医療」という新しいキャリアの選択肢が見えてくるはずです。
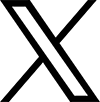
この記事が気に入った場合は
Xへポストをお願いします
