治療用アプリの市場規模はどのくらい?将来的にどこまで成長するのか
2023/02/20
2025/11/28
治療用アプリは、まだ立ち上がったばかりの新しい市場でありながら、今後10〜20年で急速な拡大が見込まれています。日本の治療用アプリ市場規模は2021年時点で約1億円とごく小さいものの、2035年には約2,850億円に達するという予測も出ています。
従来の医薬品や医療機器ではカバーしきれなかった“患者の行動変容”にアプローチできることから、製薬企業やスタートアップの参入も相次いでいます。
本記事では、治療用アプリの基本的な仕組みやヘルスケアアプリとの違いに加え、日本・海外の市場規模と成長予測、市場が拡大すると考えられる背景を整理します。将来性の高い「治療用アプリ市場」に関心のある方が、全体像をつかめる入門ガイドです。
従来の医薬品や医療機器ではカバーしきれなかった“患者の行動変容”にアプローチできることから、製薬企業やスタートアップの参入も相次いでいます。
本記事では、治療用アプリの基本的な仕組みやヘルスケアアプリとの違いに加え、日本・海外の市場規模と成長予測、市場が拡大すると考えられる背景を整理します。将来性の高い「治療用アプリ市場」に関心のある方が、全体像をつかめる入門ガイドです。
治療用アプリとはそもそも何?ヘルスケアアプリと何が違うの?
市場規模について説明する前に、治療アプリの概要と「ヘルスケアアプリ」との違いについて解説します。
治療用アプリとは、服薬や医療機器での治療ではカバーが難しい、患者の行動変容にアプローチできる治療方法です。
定期的に治療のために通院していたとしても、医療機関での診察から次の診察までの間は、空白期間になります。治療用アプリは、患者が服薬や血圧などのバイタルを入力すると、AIが医学エビデンスに基づいて解析し、病院に行かなくても治療やアドバイスを受け取れます。
特に生活習慣病などの自覚症状があまりない病気の場合、空白期間に治療へのモチベーションが下がり、治療を止めてしまう、誤った方法で服薬するといった患者は一定数いるものです。
正しい治療を続けずに放置すると、初期の段階では自覚症状がなくても、病気が進行するとさまざまな症状が現れ、最終的に命を落としてしまうケースもあります。
治療用アプリを活用することで、治療効果がアップして回復や健康維持につながります。
治療用アプリが適しているのは、糖尿病をはじめとする生活習慣病やニコチン依存症、メンタルヘルスなど、日々の行動が病状に大きな影響を与える疾患です。
治療用アプリとよく似たものに、ダイエットアプリやデジタル万歩計をはじめとするヘルスケアアプリがあります。大きな違いとして医療機器として承認を受けている点があげられます。治療用アプリは、臨床試験などを行い、医学的根拠に基づいて効果を確認しており、医師の処方があってはじめてダウンロードできます。
ヘルスケアアプリは、体重・血圧・心拍数・食事・消費カロリーなどを記録し健康管理に役立てるためのもので、病気を治療するものではありません。また、医師の処方がなくても使用できます。
(1)治療用アプリとは
治療用アプリとは、服薬や医療機器での治療ではカバーが難しい、患者の行動変容にアプローチできる治療方法です。
定期的に治療のために通院していたとしても、医療機関での診察から次の診察までの間は、空白期間になります。治療用アプリは、患者が服薬や血圧などのバイタルを入力すると、AIが医学エビデンスに基づいて解析し、病院に行かなくても治療やアドバイスを受け取れます。
特に生活習慣病などの自覚症状があまりない病気の場合、空白期間に治療へのモチベーションが下がり、治療を止めてしまう、誤った方法で服薬するといった患者は一定数いるものです。
正しい治療を続けずに放置すると、初期の段階では自覚症状がなくても、病気が進行するとさまざまな症状が現れ、最終的に命を落としてしまうケースもあります。
治療用アプリを活用することで、治療効果がアップして回復や健康維持につながります。
治療用アプリが適しているのは、糖尿病をはじめとする生活習慣病やニコチン依存症、メンタルヘルスなど、日々の行動が病状に大きな影響を与える疾患です。
(2)ヘルスケアアプリとの違いとは
治療用アプリとよく似たものに、ダイエットアプリやデジタル万歩計をはじめとするヘルスケアアプリがあります。大きな違いとして医療機器として承認を受けている点があげられます。治療用アプリは、臨床試験などを行い、医学的根拠に基づいて効果を確認しており、医師の処方があってはじめてダウンロードできます。
ヘルスケアアプリは、体重・血圧・心拍数・食事・消費カロリーなどを記録し健康管理に役立てるためのもので、病気を治療するものではありません。また、医師の処方がなくても使用できます。
日本の治療用アプリ市場規模はどのくらい?今後の予測とは
総合ビジネスマーケティング会社である富士経済が2022年に発表したプレスリリースによると、治療用アプリのうち保険適用されたものを対象とした市場規模は、2021年時点で1億円にもなります。
2022年の見込みは約2億円と2021年と比べて2倍、2035年では約2,850億円と2021年と比べると2,850倍にもなると予測されています。
日本の治療用アプリ市場は、2020年にCureAppの『CureApp SC』が医療機器として承認されたことでスタートしました。『CureApp SC』は禁煙をサポートするアプリで、日本の治療用アプリとしては初めて保険適応になりました。
日本の治療用アプリ開発はまだスタートしたばかりですが、大手製薬会社はもちろん百以上のベンチャー企業が参入しており、研究段階のアプリは急増しています。今後、多くの治療用アプリがリリースされ、急速に市場が拡大するのではないでしょうか。
治療用アプリと同じく、医療AIや医療ビックデータを活用したシステムやサービスに分類されるゲノム医療支援システム・サービス領域は、2035年の市場規模は80億円、2021年比で7.3倍に成長すると予想されています。
また、医療ビッグデータ分析サービスの2035年の市場規模の予想は746億円、2021年比で2.4倍です。
成長著しい医療AIや医療ビッグデータを活用したシステムやサービスのなかでも、特に治療用アプリは期待が持てる領域といえるでしょう。
治療用アプリ市場の将来性を理解するには、「いまどのくらいの市場規模で、いつ頃どこまで伸びそうか」を、具体的な数字で押さえておくことが重要です。
市場調査会社・富士経済の調査によると、日本の治療用アプリ(保険適用されたもの)の市場規模は、以下のように推移する見込みです。
2021年から2035年までの14年間で、年平均にすると70%を大きく超えるペースで成長していく試算です。まだ1億円規模の小さな市場である一方、将来のポテンシャルは非常に大きいと言えます。
ここで示している市場規模は、「保険適用された治療用アプリの売上」を対象とした数字です。
いわゆるデジタルセラピューティクス(DTx)全体や、自費診療のアプリ、セルフケア目的のヘルスケアアプリ、周辺のSaaS(遠隔診療システムやデータ解析サービスなど)までは含まれていません。
実際のビジネス機会としては、
●保険適用の治療用アプリ
●自費型の治療・疾患管理アプリ
●治療用アプリと連携する医療ITシステム・データ解析サービス
などを合算した「広い意味での治療用アプリ・DTx市場」を意識する必要がありますが、本記事では、比較可能な公表データにもとづき、まずは保険適用アプリの市場規模を中心に整理しています。
治療用アプリ市場が拡大すると予測されている背景には、対象疾患とプレイヤーの広がりがあります。現在は禁煙や高血圧など一部疾患が中心ですが、今後は糖尿病、不眠症、小児ADHD、メンタルヘルスなど、多様な疾患領域に広がると見込まれています。
プレイヤーの面では、
●先行している国内外スタートアップ
●既存の製薬企業・医療機器メーカー
●医療ITベンダー・SIer
などが参入しており、製薬企業とスタートアップの提携といった動きも活発になっています。新しい治療法としての有効性に加え、比較的短い開発期間・低コストで製品化できる点も、市場拡大を後押しする要因です。
2022年の見込みは約2億円と2021年と比べて2倍、2035年では約2,850億円と2021年と比べると2,850倍にもなると予測されています。
日本の治療用アプリ市場は、2020年にCureAppの『CureApp SC』が医療機器として承認されたことでスタートしました。『CureApp SC』は禁煙をサポートするアプリで、日本の治療用アプリとしては初めて保険適応になりました。
日本の治療用アプリ開発はまだスタートしたばかりですが、大手製薬会社はもちろん百以上のベンチャー企業が参入しており、研究段階のアプリは急増しています。今後、多くの治療用アプリがリリースされ、急速に市場が拡大するのではないでしょうか。
治療用アプリと同じく、医療AIや医療ビックデータを活用したシステムやサービスに分類されるゲノム医療支援システム・サービス領域は、2035年の市場規模は80億円、2021年比で7.3倍に成長すると予想されています。
また、医療ビッグデータ分析サービスの2035年の市場規模の予想は746億円、2021年比で2.4倍です。
成長著しい医療AIや医療ビッグデータを活用したシステムやサービスのなかでも、特に治療用アプリは期待が持てる領域といえるでしょう。
富士経済の予測にもとづく年次推移(日本)
治療用アプリ市場の将来性を理解するには、「いまどのくらいの市場規模で、いつ頃どこまで伸びそうか」を、具体的な数字で押さえておくことが重要です。
市場調査会社・富士経済の調査によると、日本の治療用アプリ(保険適用されたもの)の市場規模は、以下のように推移する見込みです。
| 年度 | 市場規模(日本) | 備考 |
|---|---|---|
| 2021年 | 約1億円 | 市場立ち上がり期(禁煙治療アプリなど) |
| 2022年 | 約2億円 | 2021年比で約2倍の見込み |
| 2025年 | 約210億円 | 対応疾患の拡大により急伸 |
| 2030年 | 約1,260億円 | 製薬・スタートアップの本格参入 |
| 2035年 | 約2,850億円 | 2021年比で約2,850倍に成長する予測 |
2021年から2035年までの14年間で、年平均にすると70%を大きく超えるペースで成長していく試算です。まだ1億円規模の小さな市場である一方、将来のポテンシャルは非常に大きいと言えます。
本記事で扱う「市場規模」の定義
ここで示している市場規模は、「保険適用された治療用アプリの売上」を対象とした数字です。
いわゆるデジタルセラピューティクス(DTx)全体や、自費診療のアプリ、セルフケア目的のヘルスケアアプリ、周辺のSaaS(遠隔診療システムやデータ解析サービスなど)までは含まれていません。
実際のビジネス機会としては、
●保険適用の治療用アプリ
●自費型の治療・疾患管理アプリ
●治療用アプリと連携する医療ITシステム・データ解析サービス
などを合算した「広い意味での治療用アプリ・DTx市場」を意識する必要がありますが、本記事では、比較可能な公表データにもとづき、まずは保険適用アプリの市場規模を中心に整理しています。
疾患別・プレイヤー別に見た広がりのイメージ
治療用アプリ市場が拡大すると予測されている背景には、対象疾患とプレイヤーの広がりがあります。現在は禁煙や高血圧など一部疾患が中心ですが、今後は糖尿病、不眠症、小児ADHD、メンタルヘルスなど、多様な疾患領域に広がると見込まれています。
プレイヤーの面では、
●先行している国内外スタートアップ
●既存の製薬企業・医療機器メーカー
●医療ITベンダー・SIer
などが参入しており、製薬企業とスタートアップの提携といった動きも活発になっています。新しい治療法としての有効性に加え、比較的短い開発期間・低コストで製品化できる点も、市場拡大を後押しする要因です。
海外の治療用アプリ市場規模はどのくらい?今後の予測とは
治療用アプリの開発・普及は、日本よりもアメリカの方が先行しています。2010年にリリースされた糖尿病患者向け治療補助アプリ『BlueStar』は、治療用アプリ市場にとって大きな転機となりました。
『BlueStar』は「FDA(アメリカ食品医薬局)」より、「管理医療機器」に該当するクラスⅡを取得しました。クラスⅡの取得に伴い、大手民間保険会社の保険償還となっており、患者が保険に入っていれば、一度利用料を負担後、定められた金額が戻ってきます。
『BlueStar』はアプリ単体で糖尿病の改善効果があり、治療用アプリは医薬品や医療機器による治療と並ぶ第三の治療法だと認知されるきっかけとなりました。
また、アメリカ以外の国でも治療用アプリ開発に積極的です。例えば、ドイツではすでに約40品目の医療用アプリが製品化されています。こうした背景から、グローバル市場は年率20%以上成長し、2025年には1兆円規模になるという予測もあります。
治療用アプリの開発・普及は、日本よりも米国や欧州が先行しています。糖尿病患者向け治療補助アプリ「BlueStar」がFDAの承認を受け、大手民間保険会社の償還対象となったことをきっかけに、「アプリ自体が治療効果を持つ」というコンセプトが広く認知されました。
また、ドイツでは既に約40品目の医療用アプリが製品化されており、医療制度のなかに「アプリによる治療」を組み込む取り組みが進んでいます。こうした動きを背景に、グローバル市場全体では年率20%以上の成長が続き、2025年には1兆円規模に達するという予測もあります。
日本市場は、米国や欧州と比べると立ち上がりが遅い一方で、国民皆保険制度が整っていることから「保険適用が広がれば一気にユーザーが増える」土壌があります。実際に、禁煙治療用アプリや高血圧症向けアプリが保険収載される動きが出ており、今後も対象疾患の拡大に伴って市場規模が大きく伸びると考えられます。
海外で成功した事例を日本の制度に合わせてローカライズする動きや、日本発の治療用アプリを海外へ展開する動きも増えており、グローバル市場との相互作用が日本市場の成長を後押ししていくと見込まれます。
『BlueStar』は「FDA(アメリカ食品医薬局)」より、「管理医療機器」に該当するクラスⅡを取得しました。クラスⅡの取得に伴い、大手民間保険会社の保険償還となっており、患者が保険に入っていれば、一度利用料を負担後、定められた金額が戻ってきます。
『BlueStar』はアプリ単体で糖尿病の改善効果があり、治療用アプリは医薬品や医療機器による治療と並ぶ第三の治療法だと認知されるきっかけとなりました。
また、アメリカ以外の国でも治療用アプリ開発に積極的です。例えば、ドイツではすでに約40品目の医療用アプリが製品化されています。こうした背景から、グローバル市場は年率20%以上成長し、2025年には1兆円規模になるという予測もあります。
米国・欧州を中心に拡大するグローバル市場
治療用アプリの開発・普及は、日本よりも米国や欧州が先行しています。糖尿病患者向け治療補助アプリ「BlueStar」がFDAの承認を受け、大手民間保険会社の償還対象となったことをきっかけに、「アプリ自体が治療効果を持つ」というコンセプトが広く認知されました。
また、ドイツでは既に約40品目の医療用アプリが製品化されており、医療制度のなかに「アプリによる治療」を組み込む取り組みが進んでいます。こうした動きを背景に、グローバル市場全体では年率20%以上の成長が続き、2025年には1兆円規模に達するという予測もあります。
日本市場との違いとキャッチアップの余地
日本市場は、米国や欧州と比べると立ち上がりが遅い一方で、国民皆保険制度が整っていることから「保険適用が広がれば一気にユーザーが増える」土壌があります。実際に、禁煙治療用アプリや高血圧症向けアプリが保険収載される動きが出ており、今後も対象疾患の拡大に伴って市場規模が大きく伸びると考えられます。
海外で成功した事例を日本の制度に合わせてローカライズする動きや、日本発の治療用アプリを海外へ展開する動きも増えており、グローバル市場との相互作用が日本市場の成長を後押ししていくと見込まれます。
日本の治療用アプリ市場は本当に成長する?3つのポイントを紹介
アメリカなど海外の治療用アプリ市場が拡大するなか「海外製品におされて日本市場は拡大しないのでは」と懸念を持つ人もいるかもしれません。
しかし、下記のような理由から日本の治療用アプリ市場は成長すると考えられます。
治療用アプリを開発しても、医療機器として承認され、保険適用されるかの見通しが立たないため、日本における治療用アプリへの取り組みに懸念を感じる企業は少なくありません。
厚生労働省は2021年4月に、治療用アプリの開発を後押しする「プログラム医療機器実用化促進パッケージ戦略」を本格的に開始し、参入しやすい環境を整えました。
こうした施策により、治療用アプリの開発をためらっていた企業の参入が増え、より市場が拡大しやすくなる可能性があります。
日本では全ての国民が公的医療保険に加入する「国民皆保険制度」が確立しているため、医療用アプリが保険適用になれば、原則的に3割負担で利用できます。
そのため、治療用アプリに保険が適用されれば、ユーザーの数は大幅に伸びる可能性があるでしょう。
一方、治療用アプリにおいて日本より先行しているアメリカは国民皆保険制度がなく、一部の民間保険会社でしか治療用アプリは保険適用されません。潜在的なユーザー数を考えると、日本の治療用アプリ市場には大きな期待が持てます。
高齢者が増えると医療を必要とする人の割合が高まり、医療費を支える現役世代の負担が大きくなります。また、医療従事者の数が不足し、充分な医療を提供するのが難しくなるかもしれません。
治療用アプリは、医薬品と比較して開発費が安いため、治療にかかる費用が安い傾向にあります。また、アプリ上でデータ管理などを行うことで業務効率化が実現し、リソース不足を補えます。
そのため治療用アプリのニーズが高く、市場が成長しやすいでしょう。
しかし、下記のような理由から日本の治療用アプリ市場は成長すると考えられます。
(1)厚生労働省が開発促進の施策をしている
治療用アプリを開発しても、医療機器として承認され、保険適用されるかの見通しが立たないため、日本における治療用アプリへの取り組みに懸念を感じる企業は少なくありません。
厚生労働省は2021年4月に、治療用アプリの開発を後押しする「プログラム医療機器実用化促進パッケージ戦略」を本格的に開始し、参入しやすい環境を整えました。
こうした施策により、治療用アプリの開発をためらっていた企業の参入が増え、より市場が拡大しやすくなる可能性があります。
(2)国民皆保険制度が確立している
日本では全ての国民が公的医療保険に加入する「国民皆保険制度」が確立しているため、医療用アプリが保険適用になれば、原則的に3割負担で利用できます。
そのため、治療用アプリに保険が適用されれば、ユーザーの数は大幅に伸びる可能性があるでしょう。
一方、治療用アプリにおいて日本より先行しているアメリカは国民皆保険制度がなく、一部の民間保険会社でしか治療用アプリは保険適用されません。潜在的なユーザー数を考えると、日本の治療用アプリ市場には大きな期待が持てます。
(3)少子高齢化
高齢者が増えると医療を必要とする人の割合が高まり、医療費を支える現役世代の負担が大きくなります。また、医療従事者の数が不足し、充分な医療を提供するのが難しくなるかもしれません。
治療用アプリは、医薬品と比較して開発費が安いため、治療にかかる費用が安い傾向にあります。また、アプリ上でデータ管理などを行うことで業務効率化が実現し、リソース不足を補えます。
そのため治療用アプリのニーズが高く、市場が成長しやすいでしょう。
まとめ
治療用アプリは、患者の行動変容に働きかけることで、従来の服薬や医療機器による治療だけでは届きにくかった部分にアプローチできる新しい治療法です。市場規模としては、2021年時点で日本国内は約1億円とまだ小さいものの、2035年には約2,850億円に達するという予測もあり、今後10年以上にわたって高い成長が見込まれています。
海外では米国やドイツを中心に治療用アプリの製品化が進んでおり、グローバル市場は年率20%以上のペースで拡大、2025年には1兆円規模になるとの予測もあります。日本でも、厚生労働省による開発支援策や国民皆保険制度、少子高齢化による医療ニーズの増大を背景に、治療用アプリ市場は今後本格的な成長フェーズに入っていくと考えられます。
こうした成長分野では、製薬企業や医療機器メーカーだけでなく、IT企業やスタートアップも含めて採用ニーズが高まっています。医療業界での経験を活かしたい方、ITスキルを医療に役立てたい方にとって、治療用アプリ市場は今後ますます魅力的なキャリアフィールドになっていくでしょう。治療用アプリやデジタルヘルスに積極的な企業の求人を確認しながら、将来性の高いポジションを早めに押さえておくことをおすすめします。
海外では米国やドイツを中心に治療用アプリの製品化が進んでおり、グローバル市場は年率20%以上のペースで拡大、2025年には1兆円規模になるとの予測もあります。日本でも、厚生労働省による開発支援策や国民皆保険制度、少子高齢化による医療ニーズの増大を背景に、治療用アプリ市場は今後本格的な成長フェーズに入っていくと考えられます。
こうした成長分野では、製薬企業や医療機器メーカーだけでなく、IT企業やスタートアップも含めて採用ニーズが高まっています。医療業界での経験を活かしたい方、ITスキルを医療に役立てたい方にとって、治療用アプリ市場は今後ますます魅力的なキャリアフィールドになっていくでしょう。治療用アプリやデジタルヘルスに積極的な企業の求人を確認しながら、将来性の高いポジションを早めに押さえておくことをおすすめします。
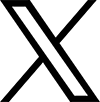
この記事が気に入った場合は
Xへポストをお願いします
