今話題のテレワークってどんな働き方?医療業界でも導入されているの?
2023/10/04
2025/11/11
オフィス以外の場所で働く「テレワーク」とは、IT業界を中心に広がりを見せる中、医療業界でも少しずつ浸透し始めています。
本記事では、テレワークとはどんな働き方か、導入によるメリット・デメリット、さらに医療業界での活用事例や注意点、セキュリティ対策まで幅広く解説。
医療系の転職を考えている方にとって、働き方を選ぶうえで参考になる内容をお届けします。
本記事では、テレワークとはどんな働き方か、導入によるメリット・デメリット、さらに医療業界での活用事例や注意点、セキュリティ対策まで幅広く解説。
医療系の転職を考えている方にとって、働き方を選ぶうえで参考になる内容をお届けします。
テレワークってそもそも何?どのくらい普及しているの?
テレワークとは、会社のオフィス以外の場所で仕事をする働き方を指しています。「tele(離れた)」と「work(働く)」を組み合わせた造語で、日本語に訳すると「遠隔勤務」という意味になります。
テレワークの普及を目指す「一般社団法人日本テレワーク協会」では、テレワークを「情報通信技術(ICT = Information and Communication Technology)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと」と定義しています。
テレワークという言葉自体は以前からあり導入している企業も存在しましたが、2020年の新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、急速に普及しました。
総務省が実施している「通信利用動向調査(企業編)」の令和元年・令和4年の調査によると、新型コロナウイルス感染拡大前の2019年は、テレワークを導入している企業は20.2%でした。新型コロナウイルスの感染拡大が発生した2020年は47.5%、2021年には51.9%と過半数に達し現在までほぼ横ばいです。
完全にテレワークで業務を行う企業もありますが、週1〜2回といったように限定的にテレワークを導入している企業も多く存在します。
※令和元年通信利用動向調査の結果
※令和4年通信利用動向調査の結果
テレワークの普及を目指す「一般社団法人日本テレワーク協会」では、テレワークを「情報通信技術(ICT = Information and Communication Technology)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと」と定義しています。
テレワークという言葉自体は以前からあり導入している企業も存在しましたが、2020年の新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、急速に普及しました。
総務省が実施している「通信利用動向調査(企業編)」の令和元年・令和4年の調査によると、新型コロナウイルス感染拡大前の2019年は、テレワークを導入している企業は20.2%でした。新型コロナウイルスの感染拡大が発生した2020年は47.5%、2021年には51.9%と過半数に達し現在までほぼ横ばいです。
完全にテレワークで業務を行う企業もありますが、週1〜2回といったように限定的にテレワークを導入している企業も多く存在します。
※令和元年通信利用動向調査の結果
※令和4年通信利用動向調査の結果
自由な時間が増える?テレワークの主なメリットを5つ紹介
テレワークの主なメリットを5つ紹介します。
テレワークであれば、通勤時間や出社準備にかかる時間が減り、その分自由な時間が増えます。特に遠距離通勤をしている人であれば通勤がなくなるだけで、プライベートの時間が大幅に増加します。
実際に、テレワークによって時間に余裕ができ、家族との時間が増えたり趣味に時間を使えるようになったりするケースも少なくありません。
テレワークを導入している企業の方が、ライフワークバランスが取りやすいといえるでしょう。
オフィスで勤務している場合は、上司・先輩・同僚の目があるため、知らず知らずの内に気が散っているケースは少なくありません。また、電話などの雑務も発生しやすく、対応に追われて業務がスムーズに進まないケースもあるでしょう。
テレワークであれば邪魔が入らないため、集中して業務に取り組めます。
育児・介護・療養など外で働くのが難しい事情があっても、在宅勤務であれば可能なケースは少なくありません。
育児・介護の場合、在宅勤務であれば家族の様子を見ながら仕事ができます。療養の場合は、通勤の必要がなく、体調と相談しながら勤務が可能です。
また、通勤がない分、時間や体力にゆとりができるのも大きなメリットです。
職場で感じるストレスのなかでも、人間関係の悩みは多くの人が抱えている問題です。相性が悪い相手であっても業務上避けられないケースが多く、長時間同じ職場で過ごすため、ストレスが大きくなりがちです。
リモートワークであれば、1人で業務に取り組む時間が長く、人間関係のストレスが大幅に軽減されます。メール・チャット・電話・Web会議などでやりとりが発生するケースもありますが、直接顔を合わせないため、出勤時よりも気にならないでしょう。
「通勤に2時間くらいかかる」「満員電車が苦痛」など、通勤によって時間や体力を奪われ、ストレスを感じている人も多いのではないでしょうか?
テレワークであれば、時間にゆとりを持てるのはもちろん、通勤による疲れやストレスを軽減できます。
(1)自由な時間が増える
テレワークであれば、通勤時間や出社準備にかかる時間が減り、その分自由な時間が増えます。特に遠距離通勤をしている人であれば通勤がなくなるだけで、プライベートの時間が大幅に増加します。
実際に、テレワークによって時間に余裕ができ、家族との時間が増えたり趣味に時間を使えるようになったりするケースも少なくありません。
テレワークを導入している企業の方が、ライフワークバランスが取りやすいといえるでしょう。
(2)集中しやすい
オフィスで勤務している場合は、上司・先輩・同僚の目があるため、知らず知らずの内に気が散っているケースは少なくありません。また、電話などの雑務も発生しやすく、対応に追われて業務がスムーズに進まないケースもあるでしょう。
テレワークであれば邪魔が入らないため、集中して業務に取り組めます。
(3)育児・介護・療養との両立がしやすい
育児・介護・療養など外で働くのが難しい事情があっても、在宅勤務であれば可能なケースは少なくありません。
育児・介護の場合、在宅勤務であれば家族の様子を見ながら仕事ができます。療養の場合は、通勤の必要がなく、体調と相談しながら勤務が可能です。
また、通勤がない分、時間や体力にゆとりができるのも大きなメリットです。
(4)人間関係のストレスが少ない
職場で感じるストレスのなかでも、人間関係の悩みは多くの人が抱えている問題です。相性が悪い相手であっても業務上避けられないケースが多く、長時間同じ職場で過ごすため、ストレスが大きくなりがちです。
リモートワークであれば、1人で業務に取り組む時間が長く、人間関係のストレスが大幅に軽減されます。メール・チャット・電話・Web会議などでやりとりが発生するケースもありますが、直接顔を合わせないため、出勤時よりも気にならないでしょう。
(5)通勤の負担が減る
「通勤に2時間くらいかかる」「満員電車が苦痛」など、通勤によって時間や体力を奪われ、ストレスを感じている人も多いのではないでしょうか?
テレワークであれば、時間にゆとりを持てるのはもちろん、通勤による疲れやストレスを軽減できます。
コミュニケーションが取りにくい?テレワークの主なデメリットを4つ紹介
テレワークの主なデメリットを4つ紹介します。
オフィスであれば、上司や同僚が近くにいるため、直接質問・相談ができます。テレワーク中のコミュニケーションは、メール・チャットツール・Web会議ツールを使用します。
メール・チャットツール・Web会議ツールでのやり取りは、対面でのコミュニケーションと比べ細かいニュアンスが伝わらず、仕事がやりにくいケースが少なくありません。
また、オフィスに出勤している時のように気軽に雑談できないため、孤独感によるメンタル不調やチームワークの低下といったリスクもあります。
特に在宅勤務の場合、周りの社員の目がなく、テレビなどの娯楽が身の回りにあるため、だらけてしまいがちです。集中力が落ち、業務効率が低下する場合もあります。
逆に、仕事に没頭しすぎて働きすぎてしまうケースもあります。
自分で仕事の進捗や労働時間を調整する必要があるため、自己管理が苦手な人はテレワークに不向きです。
オフィスは仕事に適した状態に整っていますが、自宅はそうではありません。場合によっては、インターネット回線や机、椅子といった設備が必要になります。
また、小さな子どもやペットがいる場合は、「遊ぼう」とねだられたりパソコンに触られたりと仕事に集中できない可能性があります。
テレワークで働いているとオフィスへの通勤がなくなり、その分運動量が減ってしまいます。
1日中外出せずデスクワークを続けると、運動不足による肥満や生活習慣病のリスクが増します。ジムやウォーキングなどで意識的に身体を動かすようにしましょう。
(1)コミュニケーションが取りにくい
オフィスであれば、上司や同僚が近くにいるため、直接質問・相談ができます。テレワーク中のコミュニケーションは、メール・チャットツール・Web会議ツールを使用します。
メール・チャットツール・Web会議ツールでのやり取りは、対面でのコミュニケーションと比べ細かいニュアンスが伝わらず、仕事がやりにくいケースが少なくありません。
また、オフィスに出勤している時のように気軽に雑談できないため、孤独感によるメンタル不調やチームワークの低下といったリスクもあります。
(2)自己管理が難しい
特に在宅勤務の場合、周りの社員の目がなく、テレビなどの娯楽が身の回りにあるため、だらけてしまいがちです。集中力が落ち、業務効率が低下する場合もあります。
逆に、仕事に没頭しすぎて働きすぎてしまうケースもあります。
自分で仕事の進捗や労働時間を調整する必要があるため、自己管理が苦手な人はテレワークに不向きです。
(3)自分で仕事をする環境を整えなければいけない
オフィスは仕事に適した状態に整っていますが、自宅はそうではありません。場合によっては、インターネット回線や机、椅子といった設備が必要になります。
また、小さな子どもやペットがいる場合は、「遊ぼう」とねだられたりパソコンに触られたりと仕事に集中できない可能性があります。
(4)運動不足になりやすい
テレワークで働いているとオフィスへの通勤がなくなり、その分運動量が減ってしまいます。
1日中外出せずデスクワークを続けると、運動不足による肥満や生活習慣病のリスクが増します。ジムやウォーキングなどで意識的に身体を動かすようにしましょう。
医療業界でもテレワークが普及しているって本当?現状を解説
医療業界でもテレワークが普及していますが、看護師などの医療現場で働く職種とMR・医療機器営業など医療関係の企業で働く職種では、状況が大きく異なります。
それぞれ紹介します。
医療従事者など患者と対面で接する必要のある職種の多くは出勤する必要があり、テレワークの導入が進んでいない傾向にあります。
しかし、患者と対面する必要のない業務や1人でできる業務などは、リモートワークでも対応可能です。
実際、新型コロナウイルスの感染拡大を機にオンライン診療が普及するなど、業務によってはテレワークで対応するケースも増えています。
テレワークを導入しやすい業務の例は下記の通りです。
・許可されているオンライン診療
・オンラインによる健康相談・指導
・放射線科医の読影業務など画像・ビデオ解析
・電子カルテの入力・管理
逆に、医療処置や診察など患者と対面する必要のある業務、医療機器・医薬品を取り扱う業務は、テレワークでは行えません。
医療機関によって状況が異なるので、テレワークを希望する場合は、転職活動時にしっかりチェックしましょう。
MRなど医療関係の企業で働く職種は、他の業界と同様リモートワークが推進されています。
特にMRは、新型コロナウイルスの感染拡大によって医療機関への訪問が難しくなり、Web面談による営業が増え、リモートワークが一気に広がりました。
それぞれ紹介します。
(1)医療現場で働く職種
医療従事者など患者と対面で接する必要のある職種の多くは出勤する必要があり、テレワークの導入が進んでいない傾向にあります。
しかし、患者と対面する必要のない業務や1人でできる業務などは、リモートワークでも対応可能です。
実際、新型コロナウイルスの感染拡大を機にオンライン診療が普及するなど、業務によってはテレワークで対応するケースも増えています。
テレワークを導入しやすい業務の例は下記の通りです。
・許可されているオンライン診療
・オンラインによる健康相談・指導
・放射線科医の読影業務など画像・ビデオ解析
・電子カルテの入力・管理
逆に、医療処置や診察など患者と対面する必要のある業務、医療機器・医薬品を取り扱う業務は、テレワークでは行えません。
医療機関によって状況が異なるので、テレワークを希望する場合は、転職活動時にしっかりチェックしましょう。
(2)医療関係の企業で働く職種
MRなど医療関係の企業で働く職種は、他の業界と同様リモートワークが推進されています。
特にMRは、新型コロナウイルスの感染拡大によって医療機関への訪問が難しくなり、Web面談による営業が増え、リモートワークが一気に広がりました。
テレワーク導入の成功事例と失敗事例
実際にテレワークを導入した企業では、成功しているところもあれば、逆にうまくいかなかったところもあります。ここでは、成功事例と失敗事例を紹介します。
ある医療系のシステム開発会社では、コロナ禍をきっかけに在宅勤務を本格導入。社内チャットツールの活用や、週1回のWeb雑談会などを設けたことで、社員同士のつながりも維持されています。
その結果、通勤の負担がなくなり、ライフワークバランスが改善。「仕事の満足度が上がった」という社員が8割以上になり、離職率も大幅に減少しました。
一方、テレワークの導入に失敗した企業では、業務の属人化や連携ミスが目立つようになりました。特に、「誰が何をしているのか分からない」といった声が多く、チーム内でのコミュニケーションが大きな課題に。
このような事態を防ぐには、業務の可視化やこまめな情報共有が必要です。毎朝の短いオンラインミーティングなど、工夫を取り入れることで改善が見込めます。
(1)成功事例:社員満足度の向上と離職率の減少
ある医療系のシステム開発会社では、コロナ禍をきっかけに在宅勤務を本格導入。社内チャットツールの活用や、週1回のWeb雑談会などを設けたことで、社員同士のつながりも維持されています。
その結果、通勤の負担がなくなり、ライフワークバランスが改善。「仕事の満足度が上がった」という社員が8割以上になり、離職率も大幅に減少しました。
(2)失敗事例:コミュニケーション不足による業務停滞
一方、テレワークの導入に失敗した企業では、業務の属人化や連携ミスが目立つようになりました。特に、「誰が何をしているのか分からない」といった声が多く、チーム内でのコミュニケーションが大きな課題に。
このような事態を防ぐには、業務の可視化やこまめな情報共有が必要です。毎朝の短いオンラインミーティングなど、工夫を取り入れることで改善が見込めます。
テレワークにおけるセキュリティ対策の重要性
テレワークでは、自宅やカフェなど社外で仕事をすることが多くなるため、情報漏えいなどのセキュリティリスクが高くなります。特に医療業界は個人情報を扱うケースが多いため、注意が必要です。
・公共のWi-Fiを使った作業による情報漏えい
・私用パソコンで業務をすることでのウイルス感染リスク
・紙の資料の持ち出しによる紛失や盗難
・家族や他人に画面を見られてしまうリスク など
・業務用端末にはVPNを導入して、社内ネットワークに安全にアクセスする
・クラウドサービスのアクセス権限を制限する
・ウイルス対策ソフトを必ず導入する
・セキュリティルールやガイドラインを周知する
最近では、多くの医療関連企業が「ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)」を導入し、セキュリティの強化を進めています。
(1)こんなセキュリティリスクに注意!
・公共のWi-Fiを使った作業による情報漏えい
・私用パソコンで業務をすることでのウイルス感染リスク
・紙の資料の持ち出しによる紛失や盗難
・家族や他人に画面を見られてしまうリスク など
(2)具体的な対策は?
・業務用端末にはVPNを導入して、社内ネットワークに安全にアクセスする
・クラウドサービスのアクセス権限を制限する
・ウイルス対策ソフトを必ず導入する
・セキュリティルールやガイドラインを周知する
最近では、多くの医療関連企業が「ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)」を導入し、セキュリティの強化を進めています。
まとめ
自宅・カフェ・サテライトオフィスなど会社以外で仕事をするテレワークは、すでに約5割の企業が導入しており、医療業界でも普及しつつあります。
テレワークは、自由な時間が増える・集中しやすい・育児と両立しやすいなど、メリットの大きい働き方です。ただし、コミュニケーションが取りにくい・自己管理が難しいなどのデメリットもあるため、働き方との相性を見極めることが大切です。
実際に導入している企業のなかには、「社員満足度が向上し離職率が下がった」という成功事例もあれば、「コミュニケーション不足で業務が停滞した」という失敗例もあります。成功のカギは、情報共有の仕組みや社内コミュニケーションの工夫にあります。
また、テレワークでは情報漏えいなどのセキュリティリスクもあるため、VPNの活用やセキュリティ教育など、しっかりとした対策が必要です。
医療業界では、MRをはじめとする医療関係の企業の社員はもちろん、医療従事者も少しずつテレワークで働ける場面が増えてきています。
テレワークができる転職先を探す際は、医療業界専門の転職サイトや転職エージェントの活用がおすすめです。医療業界の求人を多く保有しているため、テレワークができる職場を見つけやすいでしょう。
テレワークは、自由な時間が増える・集中しやすい・育児と両立しやすいなど、メリットの大きい働き方です。ただし、コミュニケーションが取りにくい・自己管理が難しいなどのデメリットもあるため、働き方との相性を見極めることが大切です。
実際に導入している企業のなかには、「社員満足度が向上し離職率が下がった」という成功事例もあれば、「コミュニケーション不足で業務が停滞した」という失敗例もあります。成功のカギは、情報共有の仕組みや社内コミュニケーションの工夫にあります。
また、テレワークでは情報漏えいなどのセキュリティリスクもあるため、VPNの活用やセキュリティ教育など、しっかりとした対策が必要です。
医療業界では、MRをはじめとする医療関係の企業の社員はもちろん、医療従事者も少しずつテレワークで働ける場面が増えてきています。
テレワークができる転職先を探す際は、医療業界専門の転職サイトや転職エージェントの活用がおすすめです。医療業界の求人を多く保有しているため、テレワークができる職場を見つけやすいでしょう。
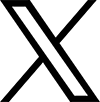
この記事が気に入った場合は
Xへポストをお願いします
