ヘルステックの市場規模とは?成長し続ける理由や注目のサービスを解説
2023/01/20
2023/01/21
ヘルステック市場は、超高齢化社会の到来や医療格差の拡大を背景に注目を集めている成長市場です。医療業界で仕事をするうえで、今後ますますヘルステックへの理解が必要となるでしょう。また、ヘルステックの現状をおさえることで、より将来性のある転職先を見極められます。
この記事では、ヘルステック市場の規模や成長する理由、注目のサービスについて紹介します。
この記事では、ヘルステック市場の規模や成長する理由、注目のサービスについて紹介します。
ヘルステックの市場規模ってどのくらい?現状を解説
ヘルステックの市場規模はどのくらいなのか、国内と海外それぞれについて解説します。
(1)国内
国内のヘルステックの市場規模を示す資料はいくつかありますが、ここでは2つの資料にもとづいて解説します。
1つ目は、総合マーケティング会社である株式会社富士経済が2019年2月に報告したプレスリリースです。プレスリリースでは、ヘルステック関連の国内市場は、2017年は2,055億円で、2022年には3,083億円に達すると予測されています。2022年には2017年と比べて5割増と急速な成長が見込まれています。
2つ目は、経済産業省が事務局を務める「次世代ヘルスケア産業協議会」が2018年に発行した「次世代ヘルスケア産業協議会の今後の方向性について」という資料です。こちらでは、民間調査会社の試算した市場規模を集計した結果、2016年の市場規模は約25兆円で、2025年には約33兆円になると予測されています。
ただし、この数字は健康志向住宅や健康関連アドバイスサービスをはじめとする将来的に新しく展開されると思われる事業は含んでいません。
ヘルスケア産業の定義や調査方法が異なるため、2つの資料の数値には大きな開きがありますが、どちらの資料でも市場規模がある程度大きく、成長市場であるとわかります。
※https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=19009&view_type=1
※https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/jisedai_healthcare/pdf/007_02_00.pdf
(2)海外
海外のヘルステック市場も、日本と同じく成長傾向にあります。特に世界に先駆けてヘルステックのニーズが高く、グローバル市場をけん引するアメリカの市場規模は、日本よりさらに大きいと考えられます。特に、ヘルスケアデータを収集し、診療時に活用する分野が盛んです。
また、イスラエルとフィンランドでも規模は小さいものの、ヘルステック分野の成長が起きています。
・イスラエル
遠隔診療に必要な情報を収集できるデバイスや、薬を飲む時間を患者に通知するスマートフォンアプリなどITを駆使したヘルステックが開発されています。
・フィンランド
退院後のがん患者の生活を支援する人工知能システムやアプリなどが普及しています。また、睡眠サイクルをモニタリングするアプリが開発されるなど、より健康な生活を送るためのヘルステック関係のサービスが増えています。
このように、アメリカを中心に海外でもヘルステックの需要は高まっており、今後も世界的に成長し続けるでしょう。
(1)国内
国内のヘルステックの市場規模を示す資料はいくつかありますが、ここでは2つの資料にもとづいて解説します。
1つ目は、総合マーケティング会社である株式会社富士経済が2019年2月に報告したプレスリリースです。プレスリリースでは、ヘルステック関連の国内市場は、2017年は2,055億円で、2022年には3,083億円に達すると予測されています。2022年には2017年と比べて5割増と急速な成長が見込まれています。
2つ目は、経済産業省が事務局を務める「次世代ヘルスケア産業協議会」が2018年に発行した「次世代ヘルスケア産業協議会の今後の方向性について」という資料です。こちらでは、民間調査会社の試算した市場規模を集計した結果、2016年の市場規模は約25兆円で、2025年には約33兆円になると予測されています。
ただし、この数字は健康志向住宅や健康関連アドバイスサービスをはじめとする将来的に新しく展開されると思われる事業は含んでいません。
ヘルスケア産業の定義や調査方法が異なるため、2つの資料の数値には大きな開きがありますが、どちらの資料でも市場規模がある程度大きく、成長市場であるとわかります。
※https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=19009&view_type=1
※https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/jisedai_healthcare/pdf/007_02_00.pdf
(2)海外
海外のヘルステック市場も、日本と同じく成長傾向にあります。特に世界に先駆けてヘルステックのニーズが高く、グローバル市場をけん引するアメリカの市場規模は、日本よりさらに大きいと考えられます。特に、ヘルスケアデータを収集し、診療時に活用する分野が盛んです。
また、イスラエルとフィンランドでも規模は小さいものの、ヘルステック分野の成長が起きています。
・イスラエル
遠隔診療に必要な情報を収集できるデバイスや、薬を飲む時間を患者に通知するスマートフォンアプリなどITを駆使したヘルステックが開発されています。
・フィンランド
退院後のがん患者の生活を支援する人工知能システムやアプリなどが普及しています。また、睡眠サイクルをモニタリングするアプリが開発されるなど、より健康な生活を送るためのヘルステック関係のサービスが増えています。
このように、アメリカを中心に海外でもヘルステックの需要は高まっており、今後も世界的に成長し続けるでしょう。
高齢化だけではない?ヘルステック市場が成長する理由とは
ヘルステック市場は世界的に成長していますが、なぜこれほどまでにニーズが伸びているのでしょうか。主な理由を紹介します。
(1)高齢化
日本では、2025年に団塊の世代にあたる約800万人が後期高齢者になり、人口の約1/4を後期高齢者が占める超高齢化社会が到来します。
医療サービスを必要とする高齢者が増えて医療費が増え、さらに医療費を負担する現役世代の割合が減るため、医療費をおさえる必要があります。
ヘルステックの活用により、医療サービスを効率化できれば、医療費の削減が期待できるでしょう。
(2)デジタル技術の進化
デジタル技術の進化によって、スマートフォンやウェアラブルデバイスなどのデジタル機器が普及し、多くの人が気軽に使えるようになりました。
端末を使って健康に関するデータを集めクラウドに送信し、AIが解析し、ユーザーにアドバイスを送るといったサービスが、アプリなどで簡単に利用できるようになったのです。
食生活・睡眠時間・心拍数・1日で歩いた距離・消費カロリーなどを収集し、病気の予防などの健康管理に役立てるサービスが増えつつあります。
(3)医療格差の解消
地理的になかなか病院に行けない、経済的な理由で受診をしにくいといった医療格差が問題になっています。地方では、医師などの医療従事者が不足しており、遠方にしか病院がない場合も少なくありません。
オンライン診療をはじめとするヘルステックは、医療格差を解消する有効な方法だと考えられています。
(4)予防医療に対する意識の高まり
「予防医療」とは、疾患にかからないように健康を維持・増進する医療です。予防医療の代表的なものとしては、人間ドックや健康診断、食生活の改善、運動などがあげられます。
現在の日本人は、ジム通いや減塩などの予防医療への関心が高く、多くの人が取り組んでおり、今後ますます注目が集まるでしょう。
デバイスで日々の食事や運動などを登録しAIが分析し改善点を提示するなど、さまざまな方法で予防医療をサポートするヘルステックサービスが開発されています。
(5)健康経営という考えの広まり
「健康経営」とは、従業員の健康管理を経営的に考えて戦略的に実践し、生産性や従業員のモチベーションアップにつなげることです。
健康経営に取り組む企業の増加に伴い、福利厚生代行サービスやメンタルヘルス管理関係のサービスが普及しています。
(1)高齢化
日本では、2025年に団塊の世代にあたる約800万人が後期高齢者になり、人口の約1/4を後期高齢者が占める超高齢化社会が到来します。
医療サービスを必要とする高齢者が増えて医療費が増え、さらに医療費を負担する現役世代の割合が減るため、医療費をおさえる必要があります。
ヘルステックの活用により、医療サービスを効率化できれば、医療費の削減が期待できるでしょう。
(2)デジタル技術の進化
デジタル技術の進化によって、スマートフォンやウェアラブルデバイスなどのデジタル機器が普及し、多くの人が気軽に使えるようになりました。
端末を使って健康に関するデータを集めクラウドに送信し、AIが解析し、ユーザーにアドバイスを送るといったサービスが、アプリなどで簡単に利用できるようになったのです。
食生活・睡眠時間・心拍数・1日で歩いた距離・消費カロリーなどを収集し、病気の予防などの健康管理に役立てるサービスが増えつつあります。
(3)医療格差の解消
地理的になかなか病院に行けない、経済的な理由で受診をしにくいといった医療格差が問題になっています。地方では、医師などの医療従事者が不足しており、遠方にしか病院がない場合も少なくありません。
オンライン診療をはじめとするヘルステックは、医療格差を解消する有効な方法だと考えられています。
(4)予防医療に対する意識の高まり
「予防医療」とは、疾患にかからないように健康を維持・増進する医療です。予防医療の代表的なものとしては、人間ドックや健康診断、食生活の改善、運動などがあげられます。
現在の日本人は、ジム通いや減塩などの予防医療への関心が高く、多くの人が取り組んでおり、今後ますます注目が集まるでしょう。
デバイスで日々の食事や運動などを登録しAIが分析し改善点を提示するなど、さまざまな方法で予防医療をサポートするヘルステックサービスが開発されています。
(5)健康経営という考えの広まり
「健康経営」とは、従業員の健康管理を経営的に考えて戦略的に実践し、生産性や従業員のモチベーションアップにつなげることです。
健康経営に取り組む企業の増加に伴い、福利厚生代行サービスやメンタルヘルス管理関係のサービスが普及しています。
ヘルステック市場ではどんなサービスが注目されているのか?
成長著しいヘルステック市場のなかでも、特に注目されているサービスを紹介します。
(1)メンタルヘルスサービス
2015年のストレスチェックの義務化や働き方改革・健康経営の推進に伴い、メンタルヘルスサービスの需要が伸びています。
また、メンタルヘルス管理のために従業員向けシステムを自社で運営していた企業がアウトソーシングする場合も見られます。
現在は、導入する企業の多くは大企業ですが、今後は中小企業にも普及し、さらにニーズが高まるでしょう。
(2)睡眠改善サービス
近年は睡眠の質が、健康や仕事などのパフォーマンスに影響するという考えが広まり、睡眠改善を目指す人が増加しています。
それに伴い、ユーザーの睡眠データを取得し睡眠改善をサポートするサービスが開発され、さらにニーズが高まると考えられます。
また、睡眠の課題があると、業務効率の低下や仕事中の事故につながりかねません。企業が従業員の睡眠改善を目指し、サービスを導入する事例も増えていくでしょう。
(3)遠隔医療
「遠隔医療」は、電話・オンラインで患者と医師をつないで健康増進や医療を提供することを指します。医療格差の解消や医療サービスの効率化につながるため、ヘルステックのなかでも特に注目されている領域です。
厚生労働省でもオンライン診療を推進する取り組みをしており、追い風が吹いているといえます。
(1)メンタルヘルスサービス
2015年のストレスチェックの義務化や働き方改革・健康経営の推進に伴い、メンタルヘルスサービスの需要が伸びています。
また、メンタルヘルス管理のために従業員向けシステムを自社で運営していた企業がアウトソーシングする場合も見られます。
現在は、導入する企業の多くは大企業ですが、今後は中小企業にも普及し、さらにニーズが高まるでしょう。
(2)睡眠改善サービス
近年は睡眠の質が、健康や仕事などのパフォーマンスに影響するという考えが広まり、睡眠改善を目指す人が増加しています。
それに伴い、ユーザーの睡眠データを取得し睡眠改善をサポートするサービスが開発され、さらにニーズが高まると考えられます。
また、睡眠の課題があると、業務効率の低下や仕事中の事故につながりかねません。企業が従業員の睡眠改善を目指し、サービスを導入する事例も増えていくでしょう。
(3)遠隔医療
「遠隔医療」は、電話・オンラインで患者と医師をつないで健康増進や医療を提供することを指します。医療格差の解消や医療サービスの効率化につながるため、ヘルステックのなかでも特に注目されている領域です。
厚生労働省でもオンライン診療を推進する取り組みをしており、追い風が吹いているといえます。
まとめ
国内のヘルステック市場は急速に成長しており、複数の調査で市場規模の大幅な拡大が予想されています。また、海外でもアメリカを中心にヘルステック市場が成長中です。背景には、高齢化やデジタル技術の進化、医療格差の解消などがあります。
ヘルステック市場のなかでも、メンタルヘルスサービス・睡眠改善サービス・遠隔医療は特に成長が期待できるでしょう。
ヘルステック関連の求人を探す場合は、一般の転職サイトよりも医療業界特化型の転職サイトがおすすめです。最先端のヘルステックを取り扱う会社など魅力的な求人が多数あります。
ヘルステック市場のなかでも、メンタルヘルスサービス・睡眠改善サービス・遠隔医療は特に成長が期待できるでしょう。
ヘルステック関連の求人を探す場合は、一般の転職サイトよりも医療業界特化型の転職サイトがおすすめです。最先端のヘルステックを取り扱う会社など魅力的な求人が多数あります。
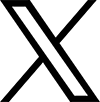
この記事が気に入った場合は
Xへポストをお願いします
