治験コーディネーターは離職率が高い?理由や対策などを解説
2025/06/04
2026/01/20
治験コーディネーター(CRC)は、医師・製薬会社・治験を受ける患者の間を取り持つ重要な役割を担っており、治験のスムーズな進行に欠かせない職種です。
医療の進歩やグローバル化などに伴い、治験コーディネーターの需要は年々高まっています。しかし、一方では「離職率が高い」と言われることがあります。
この記事では、治験コーディネーターの離職率や離職の主な理由、対策などを紹介します。
医療の進歩やグローバル化などに伴い、治験コーディネーターの需要は年々高まっています。しかし、一方では「離職率が高い」と言われることがあります。
この記事では、治験コーディネーターの離職率や離職の主な理由、対策などを紹介します。
治験コーディネーターの離職率の現状って?他職種との違いは?
治験コーディネーターの離職率の現状と、他職種との違いについて解説します。
治験コーディネーターの情報ポータルサイト「CRCばんく」によると、治験コーディネーターの近年の離職率は、おおむね7~15%程度とされています。
ただしこの数値はあくまで全体の平均値です。所属している企業・医療機関・地域・医療系資格の種類などによっても異なります。
医療機関と契約し治験業務を代行するSMO(治験施設支援機関)で働く場合と、院内CRCとして働く場合でも離職率に差があり、近年はSMOは約12~15%、院内CRCは約7~9%で推移しています。
福利厚生や労働環境の改善が進んでいるため、治験コーディネーターの離職率は低下しつつあるといわれています。
厚生労働省が実施した「令和5年雇用動向調査結果」によると、パートなどの短時間労働者以外の労働者全体の離職率は12.1%です。医療・福祉業界の離職率は、パートなどの短時間労働者を除くと13.3%です。治験コーディネーターの離職率は、平均~やや高いという結果になりました。
とはいえ大きな差はなく、「治験コーディネーターは離職率が高いから、長く続けられない仕事」とまではいえないでしょう。
(1)治験コーディネーターの離職率
治験コーディネーターの情報ポータルサイト「CRCばんく」によると、治験コーディネーターの近年の離職率は、おおむね7~15%程度とされています。
ただしこの数値はあくまで全体の平均値です。所属している企業・医療機関・地域・医療系資格の種類などによっても異なります。
医療機関と契約し治験業務を代行するSMO(治験施設支援機関)で働く場合と、院内CRCとして働く場合でも離職率に差があり、近年はSMOは約12~15%、院内CRCは約7~9%で推移しています。
福利厚生や労働環境の改善が進んでいるため、治験コーディネーターの離職率は低下しつつあるといわれています。
(2)他職種との違い
厚生労働省が実施した「令和5年雇用動向調査結果」によると、パートなどの短時間労働者以外の労働者全体の離職率は12.1%です。医療・福祉業界の離職率は、パートなどの短時間労働者を除くと13.3%です。治験コーディネーターの離職率は、平均~やや高いという結果になりました。
とはいえ大きな差はなく、「治験コーディネーターは離職率が高いから、長く続けられない仕事」とまではいえないでしょう。
治験コーディネーターの離職率の理由って?背景について解説
治験コーディネーターの離職率は、平均~やや高いくらいです。その理由について解説します。
治験コーディネーターは専門性の高い職種のため、経験を積むほど転職市場での価値が上がり、条件の良い職場ややりがいの大きい職場に転職しやすくなります。
転職してキャリアアップするのが一般的な職種である分、離職率が高くなる傾向にあります。
治験コーディネーターは、基本的に日勤のみで、夜勤・当直・オンコールがありません。手当が発生しないため、転職後に年収が下がってしまうケースがあります。
特に看護師は夜勤・当直・オンコールの手当を収入源としている人が多く、治験コーディネーターにキャリアチェンジすると、年収が減って後悔する場合が少なくありません。
また、勤務地が遠い、残業が多いなど、収入面以外の働く環境に不満を持ち、離職する人もいます。
治験コーディネーターは、医療機関と製薬会社、治験を受ける患者の調整役のため、板挟みになるケースも多くあります。
例えば、製薬会社は治験を早く進めたいと考えていても医療機関側はそれだけのリソースを確保できない、患者の要望と治験の方針が合わないといったケースです。
全ての関係者の言い分を聞き調整することに大きなストレスを感じた結果、離職を決意する治験コーディネーターもいます。
治験コーディネーターは、臨床で働くよりも患者と接する機会が少なく、患者との信頼関係構築に重きを置いている人からすると、やりがいを感じられないかもしれません。
患者の意向や利益よりも、製薬会社の方針を優先しなければならない場面もあり、「患者を救いたい」という思いが強い人にとっては、歯がゆく感じる可能性があります。
治験コーディネーターの多くは、看護師や臨床検査技師などの医療系資格や実務経験を持っています。これらの資格を持つ人は女性の割合が多いので、治験コーディネーターに占める女性の割合も高くなります。
特に30代前半~中盤くらいの女性が多く活躍しており、この世代は出産や育児などのライフステージの変化が起きる可能性が高く、それに伴う離職が多く見られます。
治験コーディネーターの仕事は、書類作成やスケジュール管理などの事務作業が多く、デスクワークが苦手な人にとっては苦痛かもしれません。
また、複数の治験を同時並行するのが一般的なので、マルチタスクで多くの業務をこなす必要があります。
医療現場での仕事とは異なるスキルが求められるため、合わないと感じて離職する人もいます。
(1)キャリアアップを目指した転職
治験コーディネーターは専門性の高い職種のため、経験を積むほど転職市場での価値が上がり、条件の良い職場ややりがいの大きい職場に転職しやすくなります。
転職してキャリアアップするのが一般的な職種である分、離職率が高くなる傾向にあります。
(2)年収など環境への不満
治験コーディネーターは、基本的に日勤のみで、夜勤・当直・オンコールがありません。手当が発生しないため、転職後に年収が下がってしまうケースがあります。
特に看護師は夜勤・当直・オンコールの手当を収入源としている人が多く、治験コーディネーターにキャリアチェンジすると、年収が減って後悔する場合が少なくありません。
また、勤務地が遠い、残業が多いなど、収入面以外の働く環境に不満を持ち、離職する人もいます。
(3)人間関係のストレス
治験コーディネーターは、医療機関と製薬会社、治験を受ける患者の調整役のため、板挟みになるケースも多くあります。
例えば、製薬会社は治験を早く進めたいと考えていても医療機関側はそれだけのリソースを確保できない、患者の要望と治験の方針が合わないといったケースです。
全ての関係者の言い分を聞き調整することに大きなストレスを感じた結果、離職を決意する治験コーディネーターもいます。
(4)やりがいを感じられない
治験コーディネーターは、臨床で働くよりも患者と接する機会が少なく、患者との信頼関係構築に重きを置いている人からすると、やりがいを感じられないかもしれません。
患者の意向や利益よりも、製薬会社の方針を優先しなければならない場面もあり、「患者を救いたい」という思いが強い人にとっては、歯がゆく感じる可能性があります。
(5)ライフステージの変化
治験コーディネーターの多くは、看護師や臨床検査技師などの医療系資格や実務経験を持っています。これらの資格を持つ人は女性の割合が多いので、治験コーディネーターに占める女性の割合も高くなります。
特に30代前半~中盤くらいの女性が多く活躍しており、この世代は出産や育児などのライフステージの変化が起きる可能性が高く、それに伴う離職が多く見られます。
(6)仕事内容が合わない
治験コーディネーターの仕事は、書類作成やスケジュール管理などの事務作業が多く、デスクワークが苦手な人にとっては苦痛かもしれません。
また、複数の治験を同時並行するのが一般的なので、マルチタスクで多くの業務をこなす必要があります。
医療現場での仕事とは異なるスキルが求められるため、合わないと感じて離職する人もいます。
治験コーディネーターとして長く働く方法って?主な対策を紹介
治験コーディネーターは離職率がやや高い傾向にありますが、工夫次第で安定して長く働けます。主な対策を紹介します。
治験コーディネーターは医師や製薬会社、治験を受ける患者の板挟みになることが多く、精神的な負担が大きい職業です。
長く働き続けるには、自分なりのストレス発散方法を見つけることが重要です。オンオフのメリハリをつけ、運動・読書・音楽鑑賞など心身をリフレッシュできる趣味を持ちましょう。
職場でのストレスを一人で抱え込まず、信頼できる同僚や上司に相談することも大切です。勤務先のメンタルヘルスサポート制度やカウンセリングサービスを積極的に活用するのも、おすすめです。
治験コーディネーターは、さまざまな立場の人と接する仕事です。医師をはじめとする医療機関のスタッフには、常に敬意を持って接し、相手の立場を理解して協力を求めることが大切です。
特にSMOから派遣される場合は、最初は外部の人として認識されているため、打ち解けにくいかもしれません。しかし業務が落ち着いているタイミングで声をかけるなど、相手が仕事をしやすいよう配慮し、自分から働きかけることで、信頼関係を築けます。
治験を受ける患者と接するときは、不安や疑問に寄り添い、わかりやすい説明を心がけることで、治験への協力を得やすくなります。患者から信頼されるようになれば、モチベーションが高まるでしょう。
また社内の同僚や上司ともこまめにコミュニケーションを取り、困った時に相談できる環境をつくることで、一人で問題を抱え込むことを避けられます。定期的に情報交換や事例の共有をすることで、チーム全体のパフォーマンス向上にも貢献できます。
治験コーディネーターを辞めたくなる理由の一つとして、事務作業やマルチタスクの負担があります。
デジタルツールを活用してタスク管理を効率化し、締め切りや重要な業務を見落とさないよう注意しましょう。業務の時間配分を見直すことで、残業時間の削減にもつながります。
書類作成やデータ入力などの事務作業は、テンプレートの活用や入力の効率化により時間短縮を図れます。
治験コーディネーターの働きやすさは、職場環境に大きく左右されます。転職を考える際は、年収だけでなく、労働時間・休日数・福利厚生・教育制度・職場の雰囲気などを総合的に評価しましょう。
離職率・平均勤続年数・教育制度・キャリアパスといった情報も、長く働ける職場かどうか見極めるポイントになります。
出産・育児を考えている場合は、リモートワークや時短勤務、フレックス制度などの導入状況も確認しておくと安心です。
転職エージェントを利用する場合は医療業界専門の会社を選び、リアルな職場環境について詳しく聞くと、ミスマッチを防ぐことができます。
(1)ストレス管理
治験コーディネーターは医師や製薬会社、治験を受ける患者の板挟みになることが多く、精神的な負担が大きい職業です。
長く働き続けるには、自分なりのストレス発散方法を見つけることが重要です。オンオフのメリハリをつけ、運動・読書・音楽鑑賞など心身をリフレッシュできる趣味を持ちましょう。
職場でのストレスを一人で抱え込まず、信頼できる同僚や上司に相談することも大切です。勤務先のメンタルヘルスサポート制度やカウンセリングサービスを積極的に活用するのも、おすすめです。
(2)良好な人間関係の構築
治験コーディネーターは、さまざまな立場の人と接する仕事です。医師をはじめとする医療機関のスタッフには、常に敬意を持って接し、相手の立場を理解して協力を求めることが大切です。
特にSMOから派遣される場合は、最初は外部の人として認識されているため、打ち解けにくいかもしれません。しかし業務が落ち着いているタイミングで声をかけるなど、相手が仕事をしやすいよう配慮し、自分から働きかけることで、信頼関係を築けます。
治験を受ける患者と接するときは、不安や疑問に寄り添い、わかりやすい説明を心がけることで、治験への協力を得やすくなります。患者から信頼されるようになれば、モチベーションが高まるでしょう。
また社内の同僚や上司ともこまめにコミュニケーションを取り、困った時に相談できる環境をつくることで、一人で問題を抱え込むことを避けられます。定期的に情報交換や事例の共有をすることで、チーム全体のパフォーマンス向上にも貢献できます。
(3)業務効率化
治験コーディネーターを辞めたくなる理由の一つとして、事務作業やマルチタスクの負担があります。
デジタルツールを活用してタスク管理を効率化し、締め切りや重要な業務を見落とさないよう注意しましょう。業務の時間配分を見直すことで、残業時間の削減にもつながります。
書類作成やデータ入力などの事務作業は、テンプレートの活用や入力の効率化により時間短縮を図れます。
(4)働きやすい職場選び
治験コーディネーターの働きやすさは、職場環境に大きく左右されます。転職を考える際は、年収だけでなく、労働時間・休日数・福利厚生・教育制度・職場の雰囲気などを総合的に評価しましょう。
離職率・平均勤続年数・教育制度・キャリアパスといった情報も、長く働ける職場かどうか見極めるポイントになります。
出産・育児を考えている場合は、リモートワークや時短勤務、フレックス制度などの導入状況も確認しておくと安心です。
転職エージェントを利用する場合は医療業界専門の会社を選び、リアルな職場環境について詳しく聞くと、ミスマッチを防ぐことができます。
まとめ
治験コーディネーターの離職率は7~15%程度で、全職種の平均よりもやや高い水準ですが、決して「長く続けられない仕事」ではありません。
離職の主な理由は、キャリアアップを目指した転職・年収をはじめとする環境への不満・人間関係のストレスなどが挙げられます。
長く働き続けるためには、適切なストレス管理、良好な人間関係の構築、業務効率化、そして働きやすい職場選びが大切です。
治験コーディネーターは専門性の高い職種であり、適切に対策することで、安定したキャリアを築けます。
転職を検討する際は、条件面だけでなく職場環境を総合的に評価し、長期的な視点で職場を選ぶことをおすすめします。
離職の主な理由は、キャリアアップを目指した転職・年収をはじめとする環境への不満・人間関係のストレスなどが挙げられます。
長く働き続けるためには、適切なストレス管理、良好な人間関係の構築、業務効率化、そして働きやすい職場選びが大切です。
治験コーディネーターは専門性の高い職種であり、適切に対策することで、安定したキャリアを築けます。
転職を検討する際は、条件面だけでなく職場環境を総合的に評価し、長期的な視点で職場を選ぶことをおすすめします。
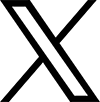
この記事が気に入った場合は
Xへポストをお願いします
