作業療法士になるにはどうすればいいの?資格取得や主な就職先を解説
2025/05/08
2026/01/09
作業療法士は、医療現場でリハビリテーションの専門家として活躍する仕事です。患者の日常生活の自立をサポートする役割を持ち、高齢化社会の進展とともに需要が高まっています。
医療機関はもちろん、介護施設や福祉施設、訪問リハビリなど活躍の場は広がりつつあります。
この記事では、作業療法士になるにはどうすればよいのかを解説。資格取得の流れや主な就職先についてまとめました。
医療機関はもちろん、介護施設や福祉施設、訪問リハビリなど活躍の場は広がりつつあります。
この記事では、作業療法士になるにはどうすればよいのかを解説。資格取得の流れや主な就職先についてまとめました。
作業療法士とはどんな仕事?役割や他のリハビリテーション職との違いを解説
作業療法士とは何かや、同じリハビリテーションの専門職である理学療法士と言語聴覚士との違いについて解説します。
作業療法士は、心身に障害のある人や高齢者に対して、日常生活動作の回復や維持、社会参加の促進を目的としたリハビリテーションを行う医療専門職です。
ここでの「作業」は、日常生活のあらゆる活動を指し、食事や入浴などの基本的な生活動作から、仕事や趣味といった社会活動まで含まれます。
作業療法士の主な役割は、患者の身体機能や認知機能を評価し、一人ひとりの状態や目標に合わせたリハビリテーションプログラムを立案・実施することです。また、病気やけがにより以前は当たり前にできていた動作ができなくなった患者の、メンタルケアも重要な仕事です。
患者の生活の質を向上させ、その人らしい生活を実現できるよう、医師や理学療法士、言語聴覚士などと連携しながら、チーム医療の一員としてリハビリテーションに取り組みます。
理学療法士は、主に起き上がる・立ち上がる・歩くといった日常生活における基本動作の改善・維持、障害の悪化の予防などを担当します。
理学療法士が身体機能にフォーカスしているのに対し、作業療法士は日常生活の動作や仕事復帰、社会参加といった生活全般の自立に重点を置きます。
例えば脳卒中で麻痺が残った患者に対し、理学療法士が歩行訓練を行う一方、作業療法士は食事や入浴などの生活動作の訓練や福祉用具の提案などをします。
また、作業療法士は身体機能のリハビリテーションだけではなく、心のリハビリテーションも行う点も理学療法士との大きな違いです。
言語聴覚士は、話すこと・聞くこと・食べることに関する機能に障害のある人に対し、リハビリテーションを行う専門職です。機能の改善・維持だけではなく、代わりとなる手段を獲得するサポートもします。
作業療法士が日常の幅広い作業を専門とするのに対し、言語聴覚士は言語や音声、食べ物を飲み込む嚥下障害に深く関わります。
(1)作業療法士とは
作業療法士は、心身に障害のある人や高齢者に対して、日常生活動作の回復や維持、社会参加の促進を目的としたリハビリテーションを行う医療専門職です。
ここでの「作業」は、日常生活のあらゆる活動を指し、食事や入浴などの基本的な生活動作から、仕事や趣味といった社会活動まで含まれます。
作業療法士の主な役割は、患者の身体機能や認知機能を評価し、一人ひとりの状態や目標に合わせたリハビリテーションプログラムを立案・実施することです。また、病気やけがにより以前は当たり前にできていた動作ができなくなった患者の、メンタルケアも重要な仕事です。
患者の生活の質を向上させ、その人らしい生活を実現できるよう、医師や理学療法士、言語聴覚士などと連携しながら、チーム医療の一員としてリハビリテーションに取り組みます。
(2)理学療法士や言語聴覚士との違い
理学療法士は、主に起き上がる・立ち上がる・歩くといった日常生活における基本動作の改善・維持、障害の悪化の予防などを担当します。
理学療法士が身体機能にフォーカスしているのに対し、作業療法士は日常生活の動作や仕事復帰、社会参加といった生活全般の自立に重点を置きます。
例えば脳卒中で麻痺が残った患者に対し、理学療法士が歩行訓練を行う一方、作業療法士は食事や入浴などの生活動作の訓練や福祉用具の提案などをします。
また、作業療法士は身体機能のリハビリテーションだけではなく、心のリハビリテーションも行う点も理学療法士との大きな違いです。
言語聴覚士は、話すこと・聞くこと・食べることに関する機能に障害のある人に対し、リハビリテーションを行う専門職です。機能の改善・維持だけではなく、代わりとなる手段を獲得するサポートもします。
作業療法士が日常の幅広い作業を専門とするのに対し、言語聴覚士は言語や音声、食べ物を飲み込む嚥下障害に深く関わります。
作業療法士になるには?国家資格について解説
作業療法士になるには、国家資格の取得が必須です。国家試験の受験資格を得る一般的なルートや国家試験の概要などについて解説します。
作業療法士の国家試験を受けるには、厚生労働省が指定する養成校(3~4年制の専門学校・3年制の短期大学・4年制大学)を卒業している、または卒業見込みでなければいけません。
養成校では、解剖学や生理学などの基礎医学、リハビリテーション医学、作業療法の理論と実践技術、臨床実習などを学びます。
医学的知識から実践的な治療技術まで幅広い内容を身につけますが、特に臨床実習は現場での経験を積む貴重な機会です。実際の患者と関わりながら技術を磨きます。
養成校を選ぶ際は、国家試験合格率や就職率、臨床実習の充実度、教員の質などを考慮することをおすすめします。幅広い知識を学びたい・大学院進学を視野に入れているといった場合は大学、専門分野に特化したい場合は専門学校が適しています。
作業療法士の国家試験は年に1回、2月に実施されます。筆記試験は北海道・宮城県・東京都・愛知県・大阪府・香川県・福岡県・沖縄県、口述試験および実技試験は東京都で行われます。合格率は例年80~90%前後です。
作業療法士の国家試験概要は下記の通りです。
<科目・試験方法>
作業療法士の国家試験の方法は大きく、筆記試験と重度視力障害者を対象とした口述試験および実技試験にわかれます。
・筆記試験
一般問題、「実地問題」と呼ばれるより臨床現場の実情に沿った問題が出題されます。
一般問題の科目は、解剖学・運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む)臨床医学大要(人間発達学を含む)および作業療法です。
実地問題の科目は、運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む)および作業療法
・口述試験および実技試験
科目は、運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む)および作業療法です。
作業療法士国家試験の合格率は高いものの、受験者は養成校で専門知識を学び、ある程度の試験対策をしてきた人ばかりです。そのため、合格するには十分な準備が必要です。
最終年度の2月に受験するため、就職先が決まってから国家試験を受けるのが一般的です。内定が出ていても、国家試験が不合格の場合、内定取り消しになる可能性があります。作業療法士を目指すのであれば、国家試験対策は必須です。
幅広い範囲から出題されるため、養成校の日々の授業内容をしっかり身につけることが大切です。また、過去問題の研究や模擬試験を通じた弱点の克服、グループ学習による知識の共有なども効果的です。
(1)国家試験の受験資格を得る方法
作業療法士の国家試験を受けるには、厚生労働省が指定する養成校(3~4年制の専門学校・3年制の短期大学・4年制大学)を卒業している、または卒業見込みでなければいけません。
養成校では、解剖学や生理学などの基礎医学、リハビリテーション医学、作業療法の理論と実践技術、臨床実習などを学びます。
医学的知識から実践的な治療技術まで幅広い内容を身につけますが、特に臨床実習は現場での経験を積む貴重な機会です。実際の患者と関わりながら技術を磨きます。
養成校を選ぶ際は、国家試験合格率や就職率、臨床実習の充実度、教員の質などを考慮することをおすすめします。幅広い知識を学びたい・大学院進学を視野に入れているといった場合は大学、専門分野に特化したい場合は専門学校が適しています。
(2)国家試験
作業療法士の国家試験は年に1回、2月に実施されます。筆記試験は北海道・宮城県・東京都・愛知県・大阪府・香川県・福岡県・沖縄県、口述試験および実技試験は東京都で行われます。合格率は例年80~90%前後です。
作業療法士の国家試験概要は下記の通りです。
<科目・試験方法>
作業療法士の国家試験の方法は大きく、筆記試験と重度視力障害者を対象とした口述試験および実技試験にわかれます。
・筆記試験
一般問題、「実地問題」と呼ばれるより臨床現場の実情に沿った問題が出題されます。
一般問題の科目は、解剖学・運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む)臨床医学大要(人間発達学を含む)および作業療法です。
実地問題の科目は、運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む)および作業療法
・口述試験および実技試験
科目は、運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む)および作業療法です。
(3)国家試験対策
作業療法士国家試験の合格率は高いものの、受験者は養成校で専門知識を学び、ある程度の試験対策をしてきた人ばかりです。そのため、合格するには十分な準備が必要です。
最終年度の2月に受験するため、就職先が決まってから国家試験を受けるのが一般的です。内定が出ていても、国家試験が不合格の場合、内定取り消しになる可能性があります。作業療法士を目指すのであれば、国家試験対策は必須です。
幅広い範囲から出題されるため、養成校の日々の授業内容をしっかり身につけることが大切です。また、過去問題の研究や模擬試験を通じた弱点の克服、グループ学習による知識の共有なども効果的です。
作業療法士の主な就職先って?仕事内容や特徴を紹介
作業療法士の代表的な勤務先である医療機関・介護施設・児童福祉施設について解説します。
作業療法士の勤務先として最も一般的なのは、病院などの医療機関です。作業療法士が働く病院には、一般病院と精神病院があります。
一般病院で働く作業療法士は、さまざまな病気やケガで機能が低下した患者に対し、作業療法を行います。一般病院は機能により、急性期病院、回復期病院、療養型病院に分類されます。
急性期病院では、発症直後のリスクを管理しつつ、機能訓練や日常生活動作訓練を行います。回復期病院では、家事や仕事復帰なども視野に入れたリハビリテーションを積極的に実施します。療養型病院では、寝返りや起き上がりなどの起居動作や移乗訓練を中心に、患者の生活能力の維持・向上を図ります。
精神病院では、統合失調症やうつ病、認知症などの患者に対して、休息やリラックス、コミュニケーション能力向上などを目的とした作業活動を実施します。
介護施設では、利用者の生活能力維持・向上のためのリハビリや日常生活支援を担います。介護老人保健施設では在宅復帰に向けた機能訓練や介護士への指導を行い、在宅が困難な人が利用する特別養護老人ホームではリハビリプログラムの指導や集団体操、レクリエーションを実施します。
その他、デイサービス・デイケアなどでも作業療法士が活躍しています。
児童発達支援センターや障害児入所施設などの児童福祉施設で、発達障害の子どもや肢体不自由な子どもが、その子らしい生活を実現するための支援をします。
具体的には、遊びや学習を通して生活動作を身につけ社会参加ができるよう、プログラムを考え実施します。保護者の相談に乗る・学習会を実施するといった保護者向け支援も重要な仕事です。
(1)医療機関
作業療法士の勤務先として最も一般的なのは、病院などの医療機関です。作業療法士が働く病院には、一般病院と精神病院があります。
一般病院で働く作業療法士は、さまざまな病気やケガで機能が低下した患者に対し、作業療法を行います。一般病院は機能により、急性期病院、回復期病院、療養型病院に分類されます。
急性期病院では、発症直後のリスクを管理しつつ、機能訓練や日常生活動作訓練を行います。回復期病院では、家事や仕事復帰なども視野に入れたリハビリテーションを積極的に実施します。療養型病院では、寝返りや起き上がりなどの起居動作や移乗訓練を中心に、患者の生活能力の維持・向上を図ります。
精神病院では、統合失調症やうつ病、認知症などの患者に対して、休息やリラックス、コミュニケーション能力向上などを目的とした作業活動を実施します。
(2)介護施設
介護施設では、利用者の生活能力維持・向上のためのリハビリや日常生活支援を担います。介護老人保健施設では在宅復帰に向けた機能訓練や介護士への指導を行い、在宅が困難な人が利用する特別養護老人ホームではリハビリプログラムの指導や集団体操、レクリエーションを実施します。
その他、デイサービス・デイケアなどでも作業療法士が活躍しています。
(3)児童福祉施設
児童発達支援センターや障害児入所施設などの児童福祉施設で、発達障害の子どもや肢体不自由な子どもが、その子らしい生活を実現するための支援をします。
具体的には、遊びや学習を通して生活動作を身につけ社会参加ができるよう、プログラムを考え実施します。保護者の相談に乗る・学習会を実施するといった保護者向け支援も重要な仕事です。
まとめ
作業療法士は、日常生活動作の回復や社会参加を支援する医療専門職です。
作業療法士になるには、資格が必須です。養成校を卒業後、国家試験に合格する必要があります。試験は毎年2月に実施され、合格率は80〜90%程度です。
主な就職先は、医療機関や介護施設、児童福祉施設などで、各現場に応じた専門的なリハビリテーションを提供します。高齢化などを背景に、作業療法士のニーズはさらに高まっています。
作業療法士になるには、資格が必須です。養成校を卒業後、国家試験に合格する必要があります。試験は毎年2月に実施され、合格率は80〜90%程度です。
主な就職先は、医療機関や介護施設、児童福祉施設などで、各現場に応じた専門的なリハビリテーションを提供します。高齢化などを背景に、作業療法士のニーズはさらに高まっています。
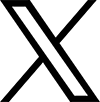
この記事が気に入った場合は
Xへポストをお願いします
