治験コーディネーターになると後悔する?仕事内容などを解説
2025/03/07
2026/01/20
治験コーディネーター(CRC)は、新薬開発に欠かせない治験をスムーズに進める役割を担う職種です。
しかし、治験コーディネーターについて調べると「辛い」「きつい」といったネガティブな声も見つかります。
この記事では、治験コーディネーターの仕事内容や治験コーディネーターになる方法、負担に感じるポイント、後悔しないための対策を紹介します。治験コーディネーターに興味のある方は、ぜひ参考にしてください。
しかし、治験コーディネーターについて調べると「辛い」「きつい」といったネガティブな声も見つかります。
この記事では、治験コーディネーターの仕事内容や治験コーディネーターになる方法、負担に感じるポイント、後悔しないための対策を紹介します。治験コーディネーターに興味のある方は、ぜひ参考にしてください。
治験コーディネーターはどんな職業?仕事内容などについて解説
治験コーディネーターは、治験をサポートする専門職です。治験とは新薬や医療機器を人間に使用し、有効性や安全性を確認する臨床試験を指します。
ここでは、治験コーディネーターの仕事内容・求められる資格について解説します。
治験コーディネーターは、医師や臨床試験を受ける患者、製薬会社の臨床開発モニター(CRA)といった関係者の間に立ち、治験がスムーズに進行するよう調整する役割を担います。
仕事をする場所は主に治験を行う医療機関で、医療機関の治験事務局の職員として働く場合と、民間企業であるSMO(治験施設支援機関)から病院で働く場合があります。
治験コーディネーターの業務は非常に多岐にわたります。主な業務は、下記の通りです
・治験実施計画書の理解
・スタートアップミーティングのサポート
・検査機器の管理・被験者募集と選別
・患者に渡す治験の説明文書と同意書の作成
・患者へのインフォームド・コンセント(事前説明)の同席
・治験スケジュールの管理
・患者のフォローアップ
・治験のデータをまとめた症例報告書(CRF)の作成
・副作用などの有害事象への対応
・治験終了報告書の作成
治験コーディネーターは専門性の高い仕事ですが、医療系の資格は必須ではありません。ただし、医学・薬学・医療制度についての知識と理解が必要なため、医療系の国家資格を持つ人材や医療機関で働いた経験のある人材が歓迎されます。
その一方、近年では未経験者の採用も増えており、特に治験施設支援機関(SMO)では、未経験者向けの研修制度を整えている企業も少なくありません。
日本SMO協会が発表した「日本SMO協会データ2023」によると、2024年3月に実施したアンケートに回答した23社で働く治験コーディネーターのうち、70%が医療系の国家資格を持っており、資格を持っていない人の割合は26.0%です。医療系の国家資格を持っていなくても、活躍するチャンスは十分あります。
ここでは、治験コーディネーターの仕事内容・求められる資格について解説します。
(1)仕事内容
治験コーディネーターは、医師や臨床試験を受ける患者、製薬会社の臨床開発モニター(CRA)といった関係者の間に立ち、治験がスムーズに進行するよう調整する役割を担います。
仕事をする場所は主に治験を行う医療機関で、医療機関の治験事務局の職員として働く場合と、民間企業であるSMO(治験施設支援機関)から病院で働く場合があります。
治験コーディネーターの業務は非常に多岐にわたります。主な業務は、下記の通りです
・治験実施計画書の理解
・スタートアップミーティングのサポート
・検査機器の管理・被験者募集と選別
・患者に渡す治験の説明文書と同意書の作成
・患者へのインフォームド・コンセント(事前説明)の同席
・治験スケジュールの管理
・患者のフォローアップ
・治験のデータをまとめた症例報告書(CRF)の作成
・副作用などの有害事象への対応
・治験終了報告書の作成
(2)求められるスキル
治験コーディネーターは専門性の高い仕事ですが、医療系の資格は必須ではありません。ただし、医学・薬学・医療制度についての知識と理解が必要なため、医療系の国家資格を持つ人材や医療機関で働いた経験のある人材が歓迎されます。
その一方、近年では未経験者の採用も増えており、特に治験施設支援機関(SMO)では、未経験者向けの研修制度を整えている企業も少なくありません。
日本SMO協会が発表した「日本SMO協会データ2023」によると、2024年3月に実施したアンケートに回答した23社で働く治験コーディネーターのうち、70%が医療系の国家資格を持っており、資格を持っていない人の割合は26.0%です。医療系の国家資格を持っていなくても、活躍するチャンスは十分あります。
治験コーディネーターになると後悔する?負担に感じる5つの理由
治験コーディネーターが「こんなはずではなかった」と後悔するのは、どのような場面なのでしょうか?仕事を負担に感じる5つの理由を紹介します。
治験コーディネーターは患者対応だけでなく、治験報告書をはじめとする治験関連の書類作成や、患者のスケジュール管理などの事務作業を担当します。
治験は厳格なルールのもとで実施されるため、書類作成時は全てのデータを正確に記録・管理する必要があります。
また、スケジュール管理にもれがあると、治験に必要な条件を満たせなくなるなどのリスクがあります。さらに治験の経過によっては、柔軟にスケジュールを変更しなければいけません。
このように事務作業や管理業務などのデスクワークが非常に多く、特にそれまで事務作業をあまり経験してこなかった治験コーディネーターは、辛いと感じる可能性があります。
治験コーディネーターは、医師・看護師・製薬会社の社員などさまざまな関係者との調整役を担っています。
そのため、プロジェクトがスタートしたばかりの頃は、人間関係ができておらず、コミュニケーションに苦労する場面が多いでしょう。
また、違う立場で働く各関係者の要望のすり合わせやスケジュール調整は、非常に気を遣うものです。
特にSMOから派遣されている場合は、ゼロから関係性を築く必要があり、ストレスを感じるかもしれません。
治験コーディネーターは、基本的にカレンダー通りの休みで夜勤もありません。しかし、治験は被験者のスケジュールに合わせて進行するため、勤務時間が不規則になりがちです。場合によっては休日出勤が必要になることもあります。
治験を受けている患者に副作用の反応が出るなどのトラブル時は、基本的に24時間以内に医師に報告しなければいけません。万が一の場合に備え、常に連絡が取れる状態でいる必要があります。
基本的に常に複数の案件を担当するため、業務量が多い傾向にあります。忙しい時期は疲れてしまい、治験コーディネーターになったことを後悔するかもしれません。
治験コーディネーターの仕事は、治験をスムーズに実施し、製薬会社の利益につなげることです。そのため、患者の希望や適性よりも、製薬会社や医療機関の意向を重視しなければいけないケースもあります。
時には「この患者さんにとって、本当に新薬は必要なのだろうか」といったジレンマを抱える場合もあります。「病気の人を助けたい」という強い想いを持つ人ほど、辛いと感じる可能性があります。
治験コーディネーターは、治験を受ける患者の健康状態や不安に向き合う仕事です。特に重篤な疾患を対象とした治験では、患者の体調悪化や死に直面し、大きな精神的ショックを受けるかもしれません。
治験中に発生した副作用の観察も重要な役割です。被験者に副作用が出た場合、その対応と報告を適切に行う必要があり、責任の重さからプレッシャーを感じる場面も多いでしょう。
(1)想像以上に事務作業が多い
治験コーディネーターは患者対応だけでなく、治験報告書をはじめとする治験関連の書類作成や、患者のスケジュール管理などの事務作業を担当します。
治験は厳格なルールのもとで実施されるため、書類作成時は全てのデータを正確に記録・管理する必要があります。
また、スケジュール管理にもれがあると、治験に必要な条件を満たせなくなるなどのリスクがあります。さらに治験の経過によっては、柔軟にスケジュールを変更しなければいけません。
このように事務作業や管理業務などのデスクワークが非常に多く、特にそれまで事務作業をあまり経験してこなかった治験コーディネーターは、辛いと感じる可能性があります。
(2)関係者とのコミュニケーションが大変である
治験コーディネーターは、医師・看護師・製薬会社の社員などさまざまな関係者との調整役を担っています。
そのため、プロジェクトがスタートしたばかりの頃は、人間関係ができておらず、コミュニケーションに苦労する場面が多いでしょう。
また、違う立場で働く各関係者の要望のすり合わせやスケジュール調整は、非常に気を遣うものです。
特にSMOから派遣されている場合は、ゼロから関係性を築く必要があり、ストレスを感じるかもしれません。
(3)ワークライフバランスが取りにくい
治験コーディネーターは、基本的にカレンダー通りの休みで夜勤もありません。しかし、治験は被験者のスケジュールに合わせて進行するため、勤務時間が不規則になりがちです。場合によっては休日出勤が必要になることもあります。
治験を受けている患者に副作用の反応が出るなどのトラブル時は、基本的に24時間以内に医師に報告しなければいけません。万が一の場合に備え、常に連絡が取れる状態でいる必要があります。
基本的に常に複数の案件を担当するため、業務量が多い傾向にあります。忙しい時期は疲れてしまい、治験コーディネーターになったことを後悔するかもしれません。
(4)利益を考慮しなければいけない
治験コーディネーターの仕事は、治験をスムーズに実施し、製薬会社の利益につなげることです。そのため、患者の希望や適性よりも、製薬会社や医療機関の意向を重視しなければいけないケースもあります。
時には「この患者さんにとって、本当に新薬は必要なのだろうか」といったジレンマを抱える場合もあります。「病気の人を助けたい」という強い想いを持つ人ほど、辛いと感じる可能性があります。
(5)精神的負担が大きい
治験コーディネーターは、治験を受ける患者の健康状態や不安に向き合う仕事です。特に重篤な疾患を対象とした治験では、患者の体調悪化や死に直面し、大きな精神的ショックを受けるかもしれません。
治験中に発生した副作用の観察も重要な役割です。被験者に副作用が出た場合、その対応と報告を適切に行う必要があり、責任の重さからプレッシャーを感じる場面も多いでしょう。
後悔しないために!治験コーディネーターへの転職での注意点
治験コーディネーターへの転職で後悔しないために、下記のような点に注意しましょう。
仕事内容・年収・ワークライフバランスなど、転職で重視するポイントは人それぞれです。キャリアの棚卸しや自己分析を通して、転職先に求める条件を整理しましょう。
とはいえ、全ての条件を満たす転職先はほぼありません。条件に優先順位をつけることで、スムーズに転職先を選べます。
転職後にギャップを感じないために、気になる勤務先がある場合は、その組織で扱っている治験の種類、担当する症例数、一人あたりの業務量などを確認しておくとよいでしょう。
また、残業や休日出勤の多さを把握して、自分のライフスタイルに合っているかもチェックすると安心です。
知り合いなどから情報収集できればベストですが、難しい場合は、医療業界専門の転職エージェントなどを通して確認する方法もおすすめです。
特に未経験から治験コーディネーターを目指す場合、入社後の教育・研修体制は非常に重要です。専門性の高い業務のため、教育・研修体制が不十分な場合、業務についていけず、大きなストレスを抱えることになります。
研修期間はどれくらいあるのか、OJTの体制はどうなっているのか、メンター制度はあるのかなど、具体的な内容について確認しておきましょう。外部研修への参加機会や資格取得支援などがあるかどうかも、長期的なキャリア形成において重要です。
(1)転職の軸を決める
仕事内容・年収・ワークライフバランスなど、転職で重視するポイントは人それぞれです。キャリアの棚卸しや自己分析を通して、転職先に求める条件を整理しましょう。
とはいえ、全ての条件を満たす転職先はほぼありません。条件に優先順位をつけることで、スムーズに転職先を選べます。
(2)具体的な業務内容や働き方を確認する
転職後にギャップを感じないために、気になる勤務先がある場合は、その組織で扱っている治験の種類、担当する症例数、一人あたりの業務量などを確認しておくとよいでしょう。
また、残業や休日出勤の多さを把握して、自分のライフスタイルに合っているかもチェックすると安心です。
知り合いなどから情報収集できればベストですが、難しい場合は、医療業界専門の転職エージェントなどを通して確認する方法もおすすめです。
(3) 教育・研修体制を確認する
特に未経験から治験コーディネーターを目指す場合、入社後の教育・研修体制は非常に重要です。専門性の高い業務のため、教育・研修体制が不十分な場合、業務についていけず、大きなストレスを抱えることになります。
研修期間はどれくらいあるのか、OJTの体制はどうなっているのか、メンター制度はあるのかなど、具体的な内容について確認しておきましょう。外部研修への参加機会や資格取得支援などがあるかどうかも、長期的なキャリア形成において重要です。
まとめ
治験コーディネーターは、治験の円滑な進行を通して、多くの人の生命や健康を支えるやりがいのある仕事です。
事務作業の多さや関係者とのコミュニケーションの大変さ、ワークライフバランスの取りにくさなどが原因で、転職前のイメージとのギャップを感じる人も少なくありません。
後悔しない転職をするためには、自己分析をしたうえで、業務内容・働き方・教育制度などをしっかりリサーチし、自分のライフスタイルや価値観に合った職場を選ぶことが大切です。
医療業界専門の転職エージェントに相談するのも方法のひとつです。豊富な治験コーディネーターの転職サポート経験をもとに、適切なアドバイスをもらえます。
事務作業の多さや関係者とのコミュニケーションの大変さ、ワークライフバランスの取りにくさなどが原因で、転職前のイメージとのギャップを感じる人も少なくありません。
後悔しない転職をするためには、自己分析をしたうえで、業務内容・働き方・教育制度などをしっかりリサーチし、自分のライフスタイルや価値観に合った職場を選ぶことが大切です。
医療業界専門の転職エージェントに相談するのも方法のひとつです。豊富な治験コーディネーターの転職サポート経験をもとに、適切なアドバイスをもらえます。
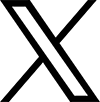
この記事が気に入った場合は
Xへポストをお願いします
