薬機法の改正ってどうなの?薬事法との違いと合わせて解説
2025/03/06
2026/01/16
薬機法は、医薬品や医療機器の品質、有効性、安全性を確保するための法律です。製薬会社や医療機器メーカーをはじめ医療業界で働くにあたって、薬機法の知識は非常に重要です。
また、薬機法の改正に伴い医療業界のマーケットが変化する可能性があるため、医療業界への転職を希望する方は、動向をしっかりチェックするのをおすすめします
薬機法は人々の生命や健康を守るために欠かせない法律です。医療技術の進歩やグローバル化、社会構造の変化などに伴い、大きな改正が行われてきました。そのため、「いつどのように改正されたのかわからない」と疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、薬機法の概要や薬事法との違い、近年の薬事法改正の内容などについて解説します。
また、薬機法の改正に伴い医療業界のマーケットが変化する可能性があるため、医療業界への転職を希望する方は、動向をしっかりチェックするのをおすすめします
薬機法は人々の生命や健康を守るために欠かせない法律です。医療技術の進歩やグローバル化、社会構造の変化などに伴い、大きな改正が行われてきました。そのため、「いつどのように改正されたのかわからない」と疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、薬機法の概要や薬事法との違い、近年の薬事法改正の内容などについて解説します。
薬機法ってそもそも何?薬事法との違いとは
最初に薬機法の概要や薬事法との違いについて解説します。
薬事法とは、医薬品や医療機器などの製造・販売などのルールを定めて、製品の品質・有効性・安全性を守り、健康被害を防ぐための法律です。
医薬品や医療機器は、身体に直接作用します。もし品質・有効性・安全性に問題があった場合は、健康が損なわれるリスクがあります。そのため薬機法で厳しく規制されています。
また、健康や美容への効果をうたって効果のない医薬品や医療機器を販売することは、消費者保護の観点から見ると、大きな問題です。一般消費者をミスリードするような広告を規制するのも、薬機法の大切な役割です。
薬機法では、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」「再生医療等製品」の5種類の製品を「医薬品等」とし、各種事業の許可や登録・広告・取扱い方法について、ルールを定めています。
薬機法に違反した場合は、下記のような罰則を受ける可能性があります。
・行政処分:製品の破棄・回収、業務停止命令、医薬品等の製造・販売に関する許可・登録の取り消しなど
・課徴金納付命令
・刑事罰:懲役や罰金
結論からいいますと、薬事法と薬機法は同じものです。2014年に「薬事法等の一部を改正する法律」が施行され、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に名称が変わりました。この法律を略して「薬機法」と呼んでいます。
今の法律では薬機法と呼びますが、長年にわたって慣れ親しんでいる薬事法も通称として使われる場合があります
この改正によって、「再生医療等製品」が新たに規制対象として導入される・診断などに用いる単体プログラム(ソフトウェア)への規制が定められるなどの変更が行われました。
(1)薬機法とは
薬事法とは、医薬品や医療機器などの製造・販売などのルールを定めて、製品の品質・有効性・安全性を守り、健康被害を防ぐための法律です。
医薬品や医療機器は、身体に直接作用します。もし品質・有効性・安全性に問題があった場合は、健康が損なわれるリスクがあります。そのため薬機法で厳しく規制されています。
また、健康や美容への効果をうたって効果のない医薬品や医療機器を販売することは、消費者保護の観点から見ると、大きな問題です。一般消費者をミスリードするような広告を規制するのも、薬機法の大切な役割です。
薬機法では、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」「再生医療等製品」の5種類の製品を「医薬品等」とし、各種事業の許可や登録・広告・取扱い方法について、ルールを定めています。
薬機法に違反した場合は、下記のような罰則を受ける可能性があります。
・行政処分:製品の破棄・回収、業務停止命令、医薬品等の製造・販売に関する許可・登録の取り消しなど
・課徴金納付命令
・刑事罰:懲役や罰金
(2)薬事法との違い
結論からいいますと、薬事法と薬機法は同じものです。2014年に「薬事法等の一部を改正する法律」が施行され、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に名称が変わりました。この法律を略して「薬機法」と呼んでいます。
今の法律では薬機法と呼びますが、長年にわたって慣れ親しんでいる薬事法も通称として使われる場合があります
この改正によって、「再生医療等製品」が新たに規制対象として導入される・診断などに用いる単体プログラム(ソフトウェア)への規制が定められるなどの変更が行われました。
薬機法の改正の内容って?近年の主な改正について解説
近年の薬機法改正でおさえておきたいポイントを施行時期別に紹介します。
・先駆け審査指定制度の法制化
先駆け審査指定制度とは、世界に先駆けて日本での申請を目指す革新的な新薬・医療機器・再生医療等製品・体外診断用医薬品を、承認審査において優先的に取り扱う制度です。
基礎研究・臨床研究や治験・承認審査・保険適用・国際展開をトータルに推進する仕組みで、2015年から試験的に実施されていましたが、2020年に薬機法の改正が施行され、法制化されました。先駆け審査指定制度を活用することで、医薬品等の実用化が、スピーディーに行えるようになります。
・条件付き早期承認制度の法制化
「条件付き早期承認制度」は、2017年から運用されていた制度ですが、2020年の9月の改正施行により法制化されました。一定の要件を満たせば、臨床試験の成績に関する資料の提出が一部免除され、スピーディーに承認が下ります。
・課徴金制度の導入
課徴金制度の導入により、医薬品等の広告で虚偽または誇大広告等の禁止に違反した場合、虚偽広告や誇大広告をしていた期間の医薬品等の売上金額の4.5%にあたる額の課徴金が課せられるようになりました。
従来は、薬機法に定められている虚偽または誇大広告の規制を破っても、逮捕されない限り、罰金を払う必要はありませんでした。虚偽広告や誇大広告によって不当な利益を得ていた企業から、利益を取り上げることで、規制の効果を高めるために改正されました。
課徴金の対象は「何人も」と定められており、製薬会社や医療機器メーカーだけではなく、メディア・広告代理店・制作会社・アフィリエイター・インスタグラマーなども規制対象に含まれています。
・法令遵守体制の整備の義務付け
薬局開設者等の許可事業者に対し、業務監督体制の整備や経営陣と現場書責任者の責任の明確化といった薬機法を遵守するための体制をつくることが義務付けられました。許可事業者による薬機法違反が起きた事例を踏まえ、違反の発生防止を目的として改正されました。
・緊急承認制度
感染症のまん延などの緊急時に、一定の条件のもとで、治療薬やワクチンの薬事承認が迅速にできるようにするための制度です。新型コロナウイルス感染症対策がきっかけで設けられました。
・電子処方箋
電子処方箋とは、これまでの紙の処方箋の代わりに、デジタルデータで処方情報を作成・管理する処方箋のことです。
電子処方箋の導入により、オンライン上で医療機関と薬局の間で処方箋をやり取りできるようになり、情報共有の効率化につながります。また、患者による紛失や有効期限切れによる再処方といった問題も解決します。患者自身が医薬品について把握できるようになり、より適切な服薬指導や健康増進に役立つと期待されています。
(1)2020年9月施行
・先駆け審査指定制度の法制化
先駆け審査指定制度とは、世界に先駆けて日本での申請を目指す革新的な新薬・医療機器・再生医療等製品・体外診断用医薬品を、承認審査において優先的に取り扱う制度です。
基礎研究・臨床研究や治験・承認審査・保険適用・国際展開をトータルに推進する仕組みで、2015年から試験的に実施されていましたが、2020年に薬機法の改正が施行され、法制化されました。先駆け審査指定制度を活用することで、医薬品等の実用化が、スピーディーに行えるようになります。
・条件付き早期承認制度の法制化
「条件付き早期承認制度」は、2017年から運用されていた制度ですが、2020年の9月の改正施行により法制化されました。一定の要件を満たせば、臨床試験の成績に関する資料の提出が一部免除され、スピーディーに承認が下ります。
(2)2021年8月施行
・課徴金制度の導入
課徴金制度の導入により、医薬品等の広告で虚偽または誇大広告等の禁止に違反した場合、虚偽広告や誇大広告をしていた期間の医薬品等の売上金額の4.5%にあたる額の課徴金が課せられるようになりました。
従来は、薬機法に定められている虚偽または誇大広告の規制を破っても、逮捕されない限り、罰金を払う必要はありませんでした。虚偽広告や誇大広告によって不当な利益を得ていた企業から、利益を取り上げることで、規制の効果を高めるために改正されました。
課徴金の対象は「何人も」と定められており、製薬会社や医療機器メーカーだけではなく、メディア・広告代理店・制作会社・アフィリエイター・インスタグラマーなども規制対象に含まれています。
・法令遵守体制の整備の義務付け
薬局開設者等の許可事業者に対し、業務監督体制の整備や経営陣と現場書責任者の責任の明確化といった薬機法を遵守するための体制をつくることが義務付けられました。許可事業者による薬機法違反が起きた事例を踏まえ、違反の発生防止を目的として改正されました。
(3)2022年5月施行
・緊急承認制度
感染症のまん延などの緊急時に、一定の条件のもとで、治療薬やワクチンの薬事承認が迅速にできるようにするための制度です。新型コロナウイルス感染症対策がきっかけで設けられました。
(4)2023年4月施行
・電子処方箋
電子処方箋とは、これまでの紙の処方箋の代わりに、デジタルデータで処方情報を作成・管理する処方箋のことです。
電子処方箋の導入により、オンライン上で医療機関と薬局の間で処方箋をやり取りできるようになり、情報共有の効率化につながります。また、患者による紛失や有効期限切れによる再処方といった問題も解決します。患者自身が医薬品について把握できるようになり、より適切な服薬指導や健康増進に役立つと期待されています。
今後も薬機法の改正が行われる!主な内容を紹介
2025年2月12日に、薬機法の改正案が閣議決定されました。主な改正内容は下記の通りです。
・一定の条件を満たした場合に薬剤師や登録販売者がいないコンビニなどの店舗で市販薬を買えるようにする
・創薬スタートアップを支援する基金を新設する
・薬局の調剤業務を一部外部委託できるようにする
・製薬会社に共有体制管理者の設置を義務付ける
・ジェネリック医薬品の安定供給を確保するための基金を設置する
医療業界でのビジネスに大きな影響を与える内容なので、今後も動向に注目しましょう。
・一定の条件を満たした場合に薬剤師や登録販売者がいないコンビニなどの店舗で市販薬を買えるようにする
・創薬スタートアップを支援する基金を新設する
・薬局の調剤業務を一部外部委託できるようにする
・製薬会社に共有体制管理者の設置を義務付ける
・ジェネリック医薬品の安定供給を確保するための基金を設置する
医療業界でのビジネスに大きな影響を与える内容なので、今後も動向に注目しましょう。
薬機法の改正に備えよう!スムーズに対応する方法とは
今後も医療や社会の状況の変化に応じて、薬機法の改正が実施されると考えられます。改正に伴い、業務フローの変更や医療業界のマーケットの変化などが発生する場合もありますが、正しい知識を持って柔軟に対応することが大切です。
薬機法の改正にスムーズに対応するには、薬機法の改正に関するニュースを追うなど、こまめに情報収集し、最新の動向をキャッチアップしましょう。
法律系・医療系メディアでも、改正内容や改正への対応方法、今後の展望などを解説している場合が多いので、チェックするのをおすすめします。
薬機法の改正にスムーズに対応するには、薬機法の改正に関するニュースを追うなど、こまめに情報収集し、最新の動向をキャッチアップしましょう。
法律系・医療系メディアでも、改正内容や改正への対応方法、今後の展望などを解説している場合が多いので、チェックするのをおすすめします。
まとめ
薬機法とは、医薬品や医療機器などの品質・有効性・安全性を守るために、製造・販売などのルールを定めた法律です。医薬品や医療機器は身体に直接作用するため、品質・有効性・安全性を確保できないと、健康被害などのリスクが発生します。
もともとは薬事法という名前でしたが、2014年の法改正により、名称が変わりました。
近年施行された薬機法の改正のなかでも特におさえておきたい内容として、先駆け審査指定制度の法制化・条件付き早期承認制度の法制化・課徴金制度の導入などがあげられます。
薬機法の知識は医療業界で仕事をするうえで、非常に重要です。改正にスムーズに対応できるよう、日頃からニュースや法律系・医療系メディアで情報収集するのをおすすめします。
もともとは薬事法という名前でしたが、2014年の法改正により、名称が変わりました。
近年施行された薬機法の改正のなかでも特におさえておきたい内容として、先駆け審査指定制度の法制化・条件付き早期承認制度の法制化・課徴金制度の導入などがあげられます。
薬機法の知識は医療業界で仕事をするうえで、非常に重要です。改正にスムーズに対応できるよう、日頃からニュースや法律系・医療系メディアで情報収集するのをおすすめします。
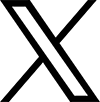
この記事が気に入った場合は
Xへポストをお願いします
