医療業界の将来性ってどうなの?転職者向けに詳しく解説
2025/02/06
2025/11/11
医療業界は、高齢化社会の進展やテクノロジーの進歩により、大きな転換期を迎えています。将来を見越してキャリアプランを立てることで、自分の市場価値を大きく高められます。
この記事では、医療業界への転職を検討されている方に向けて、業界の将来性と成長が期待される分野について詳しく解説します。キャリアプランを考える際に、ぜひ参考にして下さい。
この記事では、医療業界への転職を検討されている方に向けて、業界の将来性と成長が期待される分野について詳しく解説します。キャリアプランを考える際に、ぜひ参考にして下さい。
転職しても大丈夫?医療業界の将来性について解説
結論から言いますと、医療業界の将来性は十分あり、転職におすすめの業界です。
少子高齢化を背景に、医療ニーズは年々高まっています。さらに医療技術やITをはじめとする科学技術の進歩に伴い、新しい領域の事業も次々と誕生しています。多くの産業の拡大が停滞するなか、数少ない成長産業だといえるでしょう。
転職市場も活発で専門性が高いため、医療業界でキャリアを積むことで、市場価値を高められます。
また、営業経験者であればMRや医療機器営業、システム開発経験者であれば医療系システム開発エンジニアといったように、他業界での経験を活かせる場が多数あります。
その反面、医療従事者の人材不足や外資系企業との競争など課題も多いのが現状です。そういった課題を解決できる人材であれば、非常に高く評価されるでしょう。
少子高齢化を背景に、医療ニーズは年々高まっています。さらに医療技術やITをはじめとする科学技術の進歩に伴い、新しい領域の事業も次々と誕生しています。多くの産業の拡大が停滞するなか、数少ない成長産業だといえるでしょう。
転職市場も活発で専門性が高いため、医療業界でキャリアを積むことで、市場価値を高められます。
また、営業経験者であればMRや医療機器営業、システム開発経験者であれば医療系システム開発エンジニアといったように、他業界での経験を活かせる場が多数あります。
その反面、医療従事者の人材不足や外資系企業との競争など課題も多いのが現状です。そういった課題を解決できる人材であれば、非常に高く評価されるでしょう。
医療業界は将来性がある!その理由について解説します
医療業界に将来性がある大きな理由は、医療業界を取り巻く環境の変化です。ぜひ知っておきたい変化について解説します。
2025年には、団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者になり、日本の人口の5人に1人が後期高齢者になります。
高齢者は、病気などで医療を必要とする人の割合が多く、長期的な通院が必要な生活習慣病を患っているケースが少なくありません。特に年齢層の高い、後期高齢者では顕著です。そのため、高齢者が増えると医療ニーズが増大します。
医療ニーズが高まる一方で、現役世代の割合が減少するため、人材不足が発生します。医師や看護師などの医療従事者は以前から人材不足でしたが、今後さらに深刻化するでしょう。
また、2024年4月から医師の健康確保と長時間労働の改善を目指し、時間外労働の上限を決めるなど医師の働き方改革がさらに推進されます。働き方改革により医療現場における労働環境の改善が進められる一方で、一人あたりの労働時間が減ることで、人材不足がより問題になる可能性があります。
地域や診療科によって人材の多い・少ないに差がある点も課題です。特に外科や救急科などハードワークになりがちな診療科を志望する医師が不足しており、労働環境の改善などの取り組みが求められています。
アジアをはじめとする新興国で医療ニーズが高まるのに伴い、医療のグローバル化は加速すると考えられます。海外拠点の新設や輸入増といったビジネスの拡大が見込める反面、外資系企業との競争は激化するかもしれません
日本は、新薬や医療機器の薬事申請の承認までに時間がかかる傾向にあり、国際競争力を高めるうえでネックになる可能性があります。
また、医療機器において、内視鏡やMRIといった検査機器の国際競争力は高いものの、放射線治療装置や人工関節など治療機器のシェアは、欧米企業に大きな差をつけられています。
さらに複数の国が連携して治験を行うケースが増えており、新しい取り組みへの対応も必要です。
AI・IT技術の進歩や医療現場の人手不足などを背景に、医療業界のデジタル化は急スピードで進んでいます。
電子カルテシステムやオンライン診療、AIによる画像診断支援など、さまざまなデジタルツールが普及し、医療サービスが大きく変化している状況です。
最新技術の導入により医療の質の向上と効率化が図られており、医療従事者の業務負担軽減も期待されています。その一方新しい技術への適応などの課題もあります。
医療技術の進歩と高齢化の進展により、患者一人ひとりに求められる医療サービスは複雑化しています。特に重要なのが、治療中心の医療から予防医療へのシフトです。
予防医療とは、医療従事者の人的リソースや医療費を削減するために、病気やケガにならないように健康を維持・促進するための医療を指します。
また、在宅医療の需要が高まっており、病院完結型から地域完結型の医療体制へと移行が進んでいます。このような多様化に伴い、新しい領域の医療系事業が多数誕生すると考えられます。
(1)医療ニーズの高まり
2025年には、団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者になり、日本の人口の5人に1人が後期高齢者になります。
高齢者は、病気などで医療を必要とする人の割合が多く、長期的な通院が必要な生活習慣病を患っているケースが少なくありません。特に年齢層の高い、後期高齢者では顕著です。そのため、高齢者が増えると医療ニーズが増大します。
(2)医療従事者の人材不足
医療ニーズが高まる一方で、現役世代の割合が減少するため、人材不足が発生します。医師や看護師などの医療従事者は以前から人材不足でしたが、今後さらに深刻化するでしょう。
また、2024年4月から医師の健康確保と長時間労働の改善を目指し、時間外労働の上限を決めるなど医師の働き方改革がさらに推進されます。働き方改革により医療現場における労働環境の改善が進められる一方で、一人あたりの労働時間が減ることで、人材不足がより問題になる可能性があります。
地域や診療科によって人材の多い・少ないに差がある点も課題です。特に外科や救急科などハードワークになりがちな診療科を志望する医師が不足しており、労働環境の改善などの取り組みが求められています。
(3)医療のグローバル化
アジアをはじめとする新興国で医療ニーズが高まるのに伴い、医療のグローバル化は加速すると考えられます。海外拠点の新設や輸入増といったビジネスの拡大が見込める反面、外資系企業との競争は激化するかもしれません
日本は、新薬や医療機器の薬事申請の承認までに時間がかかる傾向にあり、国際競争力を高めるうえでネックになる可能性があります。
また、医療機器において、内視鏡やMRIといった検査機器の国際競争力は高いものの、放射線治療装置や人工関節など治療機器のシェアは、欧米企業に大きな差をつけられています。
さらに複数の国が連携して治験を行うケースが増えており、新しい取り組みへの対応も必要です。
(4)デジタル化
AI・IT技術の進歩や医療現場の人手不足などを背景に、医療業界のデジタル化は急スピードで進んでいます。
電子カルテシステムやオンライン診療、AIによる画像診断支援など、さまざまなデジタルツールが普及し、医療サービスが大きく変化している状況です。
最新技術の導入により医療の質の向上と効率化が図られており、医療従事者の業務負担軽減も期待されています。その一方新しい技術への適応などの課題もあります。
(5)医療ニーズの多様化
医療技術の進歩と高齢化の進展により、患者一人ひとりに求められる医療サービスは複雑化しています。特に重要なのが、治療中心の医療から予防医療へのシフトです。
予防医療とは、医療従事者の人的リソースや医療費を削減するために、病気やケガにならないように健康を維持・促進するための医療を指します。
また、在宅医療の需要が高まっており、病院完結型から地域完結型の医療体制へと移行が進んでいます。このような多様化に伴い、新しい領域の医療系事業が多数誕生すると考えられます。
将来性バッチリ!医療業界で特に成長が期待される分野を紹介
成長傾向にある医療業界のなかでも、特に期待されている分野に転職すれば、より充実したキャリアを歩めます。おすすめの4つの分野を紹介します。
遠隔医療とは、遠く離れた医師と患者をオンラインでつないで医療を提供する仕組みです。診療の効率化や居住エリアによる医療格差の解消に役立つため、特に大きな成長が期待されます。
新型コロナウイルスの影響で普及が加速し、医療系システム会社をはじめとするオンライン診療システムの開発・運用・データ管理などに関する事業を持つ会社が注目されています。
ウェアラブルデバイスは、スマートウォッチなど身につけて使用する端末です。ウェアラブルデバイスを着用することで、心拍数・血圧・体重・消費カロリーといった健康管理に必要なデータを自動的に蓄積できます。
自分の身体の状態を常に把握することで、健康管理がしやすくなり、生活習慣病などの予防につながります。健康管理用のアプリや治療用アプリとの連携により、さらに高度な健康管理が可能です。
また、ウェアラブルデバイスによって収集したビッグデータを活用し、病気になるリスクを予測するシステムやパーソナライズされた健康管理プログラムの作成に役立てる取り組みも進みつつあります。
画像診断AIとは、X線撮影・CT検査・MRI検査・超音波検査などで撮影した画像をAIが解析し、病変や異常の検出、診断支援を行う技術です。医師は AIの診断結果を参考にしながら、最終的な診断を下します。
深層学習を用いて大量の医用画像データから特徴を学習し、人間の医師では見落としやすい小さな変化も検出できます。
特に、がんのスクリーニングや早期発見における診断精度は高く、医師の診断を補完する重要なツールとして活用されています。
医師が手術画像を見ながら手術支援ロボットを操作することで、繊細で精密な手術ができます。手術支援ロボットの手首は人間の手首よりも可動域が広く、これまでの医師による手術と比べ、より小さな切開で手術ができ、患者の負担が軽減されます。
手術映像のデジタル記録や手術手技の定量的な評価が可能となり、医師の技術向上や教育にも活用されています。ただし、導入・維持コストが高額である、専門的なトレーニングが必要であるといった課題もあります。
(1)遠隔医療
遠隔医療とは、遠く離れた医師と患者をオンラインでつないで医療を提供する仕組みです。診療の効率化や居住エリアによる医療格差の解消に役立つため、特に大きな成長が期待されます。
新型コロナウイルスの影響で普及が加速し、医療系システム会社をはじめとするオンライン診療システムの開発・運用・データ管理などに関する事業を持つ会社が注目されています。
(2)ウェアラブルデバイス
ウェアラブルデバイスは、スマートウォッチなど身につけて使用する端末です。ウェアラブルデバイスを着用することで、心拍数・血圧・体重・消費カロリーといった健康管理に必要なデータを自動的に蓄積できます。
自分の身体の状態を常に把握することで、健康管理がしやすくなり、生活習慣病などの予防につながります。健康管理用のアプリや治療用アプリとの連携により、さらに高度な健康管理が可能です。
また、ウェアラブルデバイスによって収集したビッグデータを活用し、病気になるリスクを予測するシステムやパーソナライズされた健康管理プログラムの作成に役立てる取り組みも進みつつあります。
(3)画像診断AI
画像診断AIとは、X線撮影・CT検査・MRI検査・超音波検査などで撮影した画像をAIが解析し、病変や異常の検出、診断支援を行う技術です。医師は AIの診断結果を参考にしながら、最終的な診断を下します。
深層学習を用いて大量の医用画像データから特徴を学習し、人間の医師では見落としやすい小さな変化も検出できます。
特に、がんのスクリーニングや早期発見における診断精度は高く、医師の診断を補完する重要なツールとして活用されています。
(4)手術支援ロボット
医師が手術画像を見ながら手術支援ロボットを操作することで、繊細で精密な手術ができます。手術支援ロボットの手首は人間の手首よりも可動域が広く、これまでの医師による手術と比べ、より小さな切開で手術ができ、患者の負担が軽減されます。
手術映像のデジタル記録や手術手技の定量的な評価が可能となり、医師の技術向上や教育にも活用されています。ただし、導入・維持コストが高額である、専門的なトレーニングが必要であるといった課題もあります。
まとめ
医療業界は、少子高齢化による医療ニーズの高まりと科学技術の進歩により、確実な成長が見込まれる分野です。2025年には団塊世代が全員後期高齢者となり、医療ニーズはさらに増加します。
一方で、医療従事者の人材不足や働き方改革への対応、医療のグローバル化による国際競争の激化など、様々な課題もあります。
特に成長が期待される分野は、遠隔医療・ウェアラブルデバイスによる健康管理・AIを活用した画像診断支援・手術支援ロボットなどです。
医療業界には他業界からの転職でも、営業などこれまでのスキルを活かせる職種がたくさんあります。また、デジタル化の進展により、IT関連の知識や経験を持つ人材の需要も高まっています。
医療業界は継続的な成長が期待でき、キャリア形成の面でも魅力的な転職先といえるでしょう。
一方で、医療従事者の人材不足や働き方改革への対応、医療のグローバル化による国際競争の激化など、様々な課題もあります。
特に成長が期待される分野は、遠隔医療・ウェアラブルデバイスによる健康管理・AIを活用した画像診断支援・手術支援ロボットなどです。
医療業界には他業界からの転職でも、営業などこれまでのスキルを活かせる職種がたくさんあります。また、デジタル化の進展により、IT関連の知識や経験を持つ人材の需要も高まっています。
医療業界は継続的な成長が期待でき、キャリア形成の面でも魅力的な転職先といえるでしょう。
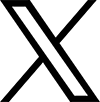
この記事が気に入った場合は
Xへポストをお願いします
