ボーナス多い業界って?ボーナスを上げる方法についても解説
2024/06/10
2025/11/11
ボーナスは、毎月の給与とは別に支給される給与のことで、ボーナスとも呼ばれます。
ボーナスがある勤務先で働いている人にとって、ボーナスは大きな楽しみのひとつです。しかし「自分のボーナスって人より多いの?少ないの?」「ボーナスを上げたい」という人も多いのではないでしょうか。
この記事では、ボーナスの平均額を年代・業界・職種ごとに紹介。さらに、ボーナスの額が決まる仕組みやボーナスアップの方法も解説します。
ボーナスがある勤務先で働いている人にとって、ボーナスは大きな楽しみのひとつです。しかし「自分のボーナスって人より多いの?少ないの?」「ボーナスを上げたい」という人も多いのではないでしょうか。
この記事では、ボーナスの平均額を年代・業界・職種ごとに紹介。さらに、ボーナスの額が決まる仕組みやボーナスアップの方法も解説します。
ボーナス多い業界って?年代・職種別の金額も紹介
最初にボーナスの平均額について、業界・年代・職種ごとの数値を含めて見ていきましょう。
厚生労働省が毎月発表している「毎月勤労統計調査」の令和5年9月分(※1)と令和6年2月分(※2)の結果速報等によると、2023年に支給された夏季賞与の平均額は39万7,129円、年末賞与(冬季賞与)の平均額は39万5,647円です。夏季賞与は前年度よりも2.0%、冬季賞与は前年度よりも0.7%増加しました。
ボーナスの金額は勤務先・職種・勤続年数・役職などによって異なりますが、一般的に「給料の〇ヶ月」といわれるように、「基本給×〇ヶ月」と基本給をベースに計算されます。基本給とは、毎月の給与から残業手当や通勤手当などの手当を引いたもので、社会保険料・税金が差し引かれる前の給与のベースとなる部分のことです。
多くの会社では、ボーナス1回あたり基本給1~2ヶ月分が支給されます。
※1 厚生労働省|毎月勤労統計調査 令和5年9月分
※2 厚生労働省|毎月勤労統計調査 令和6年2月分
厚生労働省が発表した「毎月勤労統計調査」の令和5年9月分と令和6年2月分の結果速報等より、2023年の業界別のボーナス平均額をまとめました。
冬季賞与の平均額が最も多い電気・ガス業が80万3,194円なのに対し、最も低い飲食サービス業等は6万9,234円と10倍以上の差があります。
※3 厚生労働省|毎月勤労統計調査 令和5年9月分結果速報等
厚生労働省が2024年に発表した「令和5年賃金構造基本統計調査」(※3)より、年代別の年間賞与額の平均をまとめました。
50代前半までは年齢が上がるのに伴い年間賞与額も増加し、50代後半からは逆に年齢が上がるにつれ年間賞与額も減少していきます。
年代別のデータからは、ボーナスの金額は年齢・勤続年数に大きく左右されることがわかります。
※3 厚生労働省|令和5年賃金構造基本統計調査
大手求人サイト「doda」が2023年に発表した「ボーナス平均支給額の実態調査【最新版】(冬・夏、年代別、職種別の賞与)」によると、賞与の平均額が高い職種のTOP5は下記の通りです。
「毎月勤労統計調査」によると年間賞与の平均額は約80万円なので、職種によっては平均よりも大幅に高い金額になることがわかります。
※4 doda|「ボーナス平均支給額の実態調査【最新版】(冬・夏、年代別、職種別の賞与)」
(1)ボーナスの平均額は約40万円
厚生労働省が毎月発表している「毎月勤労統計調査」の令和5年9月分(※1)と令和6年2月分(※2)の結果速報等によると、2023年に支給された夏季賞与の平均額は39万7,129円、年末賞与(冬季賞与)の平均額は39万5,647円です。夏季賞与は前年度よりも2.0%、冬季賞与は前年度よりも0.7%増加しました。
ボーナスの金額は勤務先・職種・勤続年数・役職などによって異なりますが、一般的に「給料の〇ヶ月」といわれるように、「基本給×〇ヶ月」と基本給をベースに計算されます。基本給とは、毎月の給与から残業手当や通勤手当などの手当を引いたもので、社会保険料・税金が差し引かれる前の給与のベースとなる部分のことです。
多くの会社では、ボーナス1回あたり基本給1~2ヶ月分が支給されます。
※1 厚生労働省|毎月勤労統計調査 令和5年9月分
※2 厚生労働省|毎月勤労統計調査 令和6年2月分
(2)ボーナス金額は業界による差が大きい
厚生労働省が発表した「毎月勤労統計調査」の令和5年9月分と令和6年2月分の結果速報等より、2023年の業界別のボーナス平均額をまとめました。
冬季賞与の平均額が最も多い電気・ガス業が80万3,194円なのに対し、最も低い飲食サービス業等は6万9,234円と10倍以上の差があります。
| 業種 | 夏季賞与の平均額 | 冬季賞与の平均額 |
|---|---|---|
| 鉱業、採石業等 | 55万1,276円 | 58万1,210円 |
| 建設業 | 54万695円 | 49万9,260円 |
| 製造業 | 53万5,180円 | 52万3,946円 |
| 電気・ガス業 | 74万5,209円 | 80万3,194円 |
| 情報通信業 | 70万8,645円 | 71万3,851円 |
| 運輸業、郵便業 | 38万7,908円 | 41万1,790円 |
| 卸売業、小売業 | 35万8,409円 | 36万7,165円 |
| 金融業、保険業 | 66万7,956円 | 64万5,024円 |
| 不動産・物品賃貸業 | 65万6,400円 | 54万8,808円 |
| 学術研究等 | 69万847円 | 63万490円 |
| 飲食サービス業等 | 5万9,978円 | 6万9,234円 |
| 生活関連サービス等 | 18万6,583円 | 17万269円 |
| 教育、学習支援業 | 52万2,001円 | 53万5,395円 |
| 医療、福祉 | 27万804円 | 29万826円 |
| 複合サービス事業 | 42万5,769円 | 45万9,608円 |
| その他のサービス業 | 23万8,013円 | 23万9,074円 |
| 全業種の平均 | 39万7,129円 | 39万5,647円 |
(3)年間賞与額は50代前半がピーク
厚生労働省が2024年に発表した「令和5年賃金構造基本統計調査」(※3)より、年代別の年間賞与額の平均をまとめました。
50代前半までは年齢が上がるのに伴い年間賞与額も増加し、50代後半からは逆に年齢が上がるにつれ年間賞与額も減少していきます。
年代別のデータからは、ボーナスの金額は年齢・勤続年数に大きく左右されることがわかります。
| 年代 | 年間賞与の平均額 |
|---|---|
| ~19歳 | 14万8,700円 |
| 20~24歳 | 37万8,900円 |
| 25~29歳 | 66万3,100円 |
| 30~34歳 | 80万2,100円 |
| 35~39歳 | 93万8,100円 |
| 40~44歳 | 103万900円 |
| 45~49歳 | 111万9,800円 |
| 50~54歳 | 119万6,300円 |
| 55~59歳 | 121万9,100円 |
| 60~64歳 | 72万3,600円 |
| 65~69歳 | 36万2,000円 |
| 70歳~ | 27万300円 |
※3 厚生労働省|令和5年賃金構造基本統計調査
(4)エンジニア系は平均賞与額が高い
大手求人サイト「doda」が2023年に発表した「ボーナス平均支給額の実態調査【最新版】(冬・夏、年代別、職種別の賞与)」によると、賞与の平均額が高い職種のTOP5は下記の通りです。
「毎月勤労統計調査」によると年間賞与の平均額は約80万円なので、職種によっては平均よりも大幅に高い金額になることがわかります。
| 順位 | 職種 | 年間賞与の平均額 |
|---|---|---|
| 1 | 製品企画 | 174万8,000円 |
| 2 | 法務・知的財産・特許 | 170万3,000円 |
| 3 | 基礎研究 | 169万5,000円 |
| 4 | MR | 163万2,000円 |
| 5 | 経営企画・事業企画 | 162万9,000円 |
※4 doda|「ボーナス平均支給額の実態調査【最新版】(冬・夏、年代別、職種別の賞与)」
ボーナスは3種類!それぞれの金額の決め方を解説
ボーナス額の決め方は、勤務先によって異なります。ここでは代表的な3種類について解説します。
毎月の基本給をもとにボーナス額を決める方法です。「基本給×〇ヶ月」の計算式で算出した金額が支払われます。多くの企業が導入しており、年2回、夏季・冬季に支給されるのが一般的です。
成果をもとに金額を計算する賞与です。会社全体・部署の業績や個人の成績によって支給額が変わるため、社員の意欲向上につながります。特に外資系企業で取り入れられていますが、近年は日本企業でも導入するケースが増えています。
決算月前後の業績をもとに支給額が決まります。利益が出ていない場合は支給されない可能性もある賞与です。夏季・冬季と別に支給する会社もあれば、決算賞与のみの会社もあります。仕事の成果がボーナスに直結するので、社員のモチベーションアップにつながりやすい点が特徴です。
(1)基本給連動型賞与
毎月の基本給をもとにボーナス額を決める方法です。「基本給×〇ヶ月」の計算式で算出した金額が支払われます。多くの企業が導入しており、年2回、夏季・冬季に支給されるのが一般的です。
(2)業績連動型賞与
成果をもとに金額を計算する賞与です。会社全体・部署の業績や個人の成績によって支給額が変わるため、社員の意欲向上につながります。特に外資系企業で取り入れられていますが、近年は日本企業でも導入するケースが増えています。
(3)決算賞与
決算月前後の業績をもとに支給額が決まります。利益が出ていない場合は支給されない可能性もある賞与です。夏季・冬季と別に支給する会社もあれば、決算賞与のみの会社もあります。仕事の成果がボーナスに直結するので、社員のモチベーションアップにつながりやすい点が特徴です。
ボーナスを上げるにはどうしたらいいの?7つの方法を紹介
「今よりもボーナスを上げたい」という方向けに、おすすめの方法を7つ紹介します。
社内で成果を出すことで、評価が高まり、ボーナスアップにつながります。特に業績連動型賞与や決算賞与の場合は、成果がダイレクトに金額に反映されるので、大幅アップも可能です。
基本給連動型賞与であっても、高評価によってボーナス計算のベースとなる基本給が上がれば、より高い金額が支給されます。
なかでも重要なのは、数字で表すことができる成果です。売上目標の達成率・コスト削減額・業務効率化による時間短縮率など客観的な成果を提示できれば、ボーナスを上げてもらえる可能性は高いでしょう。
多くの企業では目標管理制度を採用しており、期初に設定した目標に対する達成度がボーナス査定に直結します。そのため「前年比120%の売上達成」「工数を30%削減」といった具体的な数値実績は、明確な判断材料となります。
面談の場など上司と話す際は、具体的な数値を提示するようにすると効果的です。
同じ会社でも、ボーナスが上がりやすい業務と上がりにくい業務があります。一般的に、営業部門など売上や利益に直結するポジションの方が、成果次第でボーナスが上がりやすい傾向にあります。
逆に事務職などバックオフィス系は、売上や利益に直結しない分、大きなボーナスアップは難しいといえます。営業職などへの異動のチャンスがあれば、引き受けるのも方法のひとつです。
現在の部署内でも、収益につながるプロジェクトに積極的に参加することで、会社への貢献度を高められ、ボーナスアップにつながるかもしれません。
自社のビジネスモデルを理解し、どの業務が売上や利益を生んでいるかを見極めることが重要です。
スキルアップして市場価値を高めることで社内評価が上がり、ボーナスアップにつながる可能性があります。
IT業界であればクラウド関連の認定資格、金融業界であれば証券アナリスト、会計分野であれば税理士や公認会計士など、専門性を証明する資格の取得は強力な武器になります。
特に看護師をはじめとする医療従事者など数値で成果を示しにくい職種の場合、資格取得は客観的にスキルをアピールする材料として非常に有効です。
資格手当をもらえる職場も多いですがそれだけでなく、高度な専門性を持つ人材として評価され、給与やボーナスに反映されます。新しい技術やトレンドに関するスキルを習得することで、社内での価値が高まり、ボーナスアップを交渉しやすくなります。
多くの企業では、役職や等級が上がるほどボーナスの基準額や支給率が高くなる仕組みになっています。マネージャーや課長、部長といった管理職に昇進することで、基本給のアップだけでなく、ボーナスの大幅な増加につながります。
また、専門職系の等級制度を設けている職場では、専門性の高さに応じた等級アップでもボーナスが増額します。
昇進・昇格には、リーダーシップの発揮、後輩の育成、部門を超えた横断的な取り組みへの参加など現在の職域以上の貢献が求められます。マネジメント経験は、社内はもちろん、転職市場でも高く評価されるので、積極的に昇進・昇格を目指しましょう。
自分では努力して成果を出しているつもりでも、職場の評価制度に沿って行動していないと、高評価につながらない場合があります。
職場の評価制度を確認し、基準や運営ルールに合わせて仕事に取り組むことで、ボーナスが上がるかもしれません。
もし評価制度をよく確認してもわからない点があれば、上司に評価を上げる方法を質問してみましょう。部下の評価が上がるのは上司にとってもプラスなので、快く教えてもらえるでしょう。
ボーナスの評価は最終的に人が行うものです。どれだけ優れた成果を出していても、上司や評価者に伝わっていなければ、正当な評価は得られません。
1on1ミーティングなどの機会を活用し、上司や評価者に自分の成果や取り組みを定期的に共有しましょう。特に、困難を乗り越えた経験や、チームへの貢献、顧客からの高評価など、数字だけでは見えない成果は自分から伝えると効果的です。
評価期間の終盤だけでなく、期間の初めから計画的に成果を可視化し、中間面談などの機会を活用して進捗状況を共有することで、強くアピールできます。
ボーナス額は、業界や職種によってある程度決まっています。また、勤務先のボーナス額の決め方によっても異なります。
そのため、今の職場で努力しても賞与が上がらないケースも少なくありません。より賞与を多くもらえる職場に転職するのも方法のひとつです。
(1)社内で成果を出す
社内で成果を出すことで、評価が高まり、ボーナスアップにつながります。特に業績連動型賞与や決算賞与の場合は、成果がダイレクトに金額に反映されるので、大幅アップも可能です。
基本給連動型賞与であっても、高評価によってボーナス計算のベースとなる基本給が上がれば、より高い金額が支給されます。
なかでも重要なのは、数字で表すことができる成果です。売上目標の達成率・コスト削減額・業務効率化による時間短縮率など客観的な成果を提示できれば、ボーナスを上げてもらえる可能性は高いでしょう。
多くの企業では目標管理制度を採用しており、期初に設定した目標に対する達成度がボーナス査定に直結します。そのため「前年比120%の売上達成」「工数を30%削減」といった具体的な数値実績は、明確な判断材料となります。
面談の場など上司と話す際は、具体的な数値を提示するようにすると効果的です。
(2)会社の収益に直結する業務にシフトする
同じ会社でも、ボーナスが上がりやすい業務と上がりにくい業務があります。一般的に、営業部門など売上や利益に直結するポジションの方が、成果次第でボーナスが上がりやすい傾向にあります。
逆に事務職などバックオフィス系は、売上や利益に直結しない分、大きなボーナスアップは難しいといえます。営業職などへの異動のチャンスがあれば、引き受けるのも方法のひとつです。
現在の部署内でも、収益につながるプロジェクトに積極的に参加することで、会社への貢献度を高められ、ボーナスアップにつながるかもしれません。
自社のビジネスモデルを理解し、どの業務が売上や利益を生んでいるかを見極めることが重要です。
(3)スキルアップして市場価値を高める
スキルアップして市場価値を高めることで社内評価が上がり、ボーナスアップにつながる可能性があります。
IT業界であればクラウド関連の認定資格、金融業界であれば証券アナリスト、会計分野であれば税理士や公認会計士など、専門性を証明する資格の取得は強力な武器になります。
特に看護師をはじめとする医療従事者など数値で成果を示しにくい職種の場合、資格取得は客観的にスキルをアピールする材料として非常に有効です。
資格手当をもらえる職場も多いですがそれだけでなく、高度な専門性を持つ人材として評価され、給与やボーナスに反映されます。新しい技術やトレンドに関するスキルを習得することで、社内での価値が高まり、ボーナスアップを交渉しやすくなります。
(4)昇進・昇格を目指す
多くの企業では、役職や等級が上がるほどボーナスの基準額や支給率が高くなる仕組みになっています。マネージャーや課長、部長といった管理職に昇進することで、基本給のアップだけでなく、ボーナスの大幅な増加につながります。
また、専門職系の等級制度を設けている職場では、専門性の高さに応じた等級アップでもボーナスが増額します。
昇進・昇格には、リーダーシップの発揮、後輩の育成、部門を超えた横断的な取り組みへの参加など現在の職域以上の貢献が求められます。マネジメント経験は、社内はもちろん、転職市場でも高く評価されるので、積極的に昇進・昇格を目指しましょう。
(5)職場の評価制度を確認してその通りに行動する
自分では努力して成果を出しているつもりでも、職場の評価制度に沿って行動していないと、高評価につながらない場合があります。
職場の評価制度を確認し、基準や運営ルールに合わせて仕事に取り組むことで、ボーナスが上がるかもしれません。
もし評価制度をよく確認してもわからない点があれば、上司に評価を上げる方法を質問してみましょう。部下の評価が上がるのは上司にとってもプラスなので、快く教えてもらえるでしょう。
(6)上司や評価者とコミュニケーションを取る
ボーナスの評価は最終的に人が行うものです。どれだけ優れた成果を出していても、上司や評価者に伝わっていなければ、正当な評価は得られません。
1on1ミーティングなどの機会を活用し、上司や評価者に自分の成果や取り組みを定期的に共有しましょう。特に、困難を乗り越えた経験や、チームへの貢献、顧客からの高評価など、数字だけでは見えない成果は自分から伝えると効果的です。
評価期間の終盤だけでなく、期間の初めから計画的に成果を可視化し、中間面談などの機会を活用して進捗状況を共有することで、強くアピールできます。
(7)転職する
ボーナス額は、業界や職種によってある程度決まっています。また、勤務先のボーナス額の決め方によっても異なります。
そのため、今の職場で努力しても賞与が上がらないケースも少なくありません。より賞与を多くもらえる職場に転職するのも方法のひとつです。
転職でボーナスを上げたい人へ!高いボーナスがもらえる職場とは
転職をすることでボーナスを上げるには、職場選びが重要です。高いボーナスをもらえる会社の特徴を紹介します。
ボーナス額は業界によって大きく異なります。働く業界にこだわりがない場合は、ボーナス額の高い業界にキャリアチェンジするのも方法のひとつです。
ただし、他業界の会社の実情を把握するのは難しいものです。ボーナス額が高くても、月収が少ない・福利厚生が手薄である・激務でワークライフバランスが取りにくい・仕事が合わないといったデメリットがあるかもしれません。
ボーナス額だけに捉われず、総合的に見てメリットが大きい職場を選びましょう。
同じ業界であっても、一般的に基本給が高い会社ほど、ボーナス額が高い傾向にあります。業界の給料ランキングなどをチェックして、業績の良い会社を選ぶようにしましょう。
ただし、ボーナスは基本給や会社の業績、社会の状況によって上下します。今は基本給がそれほど高くなくても、将来的に成長が見込める会社であればゆくゆくは業績が伸び、基本給が上がり、高いボーナスが期待できるかもしれません。
業界の状況にアンテナを張り、将来性も考慮したうえで、転職先を選びましょう。
企業によってボーナスの仕組みは大きく異なります。基本給の何ヶ月分という固定的な算定方法よりも、業績連動型のボーナス制度を採用している企業の方が、成果次第で高いボーナスを獲得できる可能性があります。
営業職など目に見える成果を出しやすい職種の場合、業績連動型賞与や決算賞与の会社に転職することで、大幅に賞与が上がる可能性があります。
特に外資系企業や成長中のベンチャー企業では、会社や個人の業績に応じて大きく変動するインセンティブ制度を導入していることが多く、好業績時には年収の30〜50%がボーナスとして支給されるケースもあります。
ただし業績連動型の場合、会社の業績や自分の成果によっては、ボーナスが極端に低くなる可能性もあります。自身の能力と職場の成長性を見極めることが大切です。
早くボーナスを上げたい場合やスキルに自信がある場合は、実力主義の会社がおすすめです。外資系企業やベンチャー企業など実力主義の会社であれば、年次・年齢に関係なく、成果次第で、どんどん昇格・昇給していき、ボーナスもアップします。
逆に年功序列の会社の場合は、希望するボーナス額に達するまで何年もかかるかもしれません。
ボーナスアップを目指して転職する場合は、転職エージェントに相談するのがおすすめです。希望に合った求人を紹介してくれるだけではなく、選考対策や入社時の条件交渉などのサポートを受けられます。条件交渉に成功すれば、より高額の賞与がもらえる可能性があります。
(1)ボーナス額の多い業界の会社
ボーナス額は業界によって大きく異なります。働く業界にこだわりがない場合は、ボーナス額の高い業界にキャリアチェンジするのも方法のひとつです。
ただし、他業界の会社の実情を把握するのは難しいものです。ボーナス額が高くても、月収が少ない・福利厚生が手薄である・激務でワークライフバランスが取りにくい・仕事が合わないといったデメリットがあるかもしれません。
ボーナス額だけに捉われず、総合的に見てメリットが大きい職場を選びましょう。
(2)基本給が良い会社
同じ業界であっても、一般的に基本給が高い会社ほど、ボーナス額が高い傾向にあります。業界の給料ランキングなどをチェックして、業績の良い会社を選ぶようにしましょう。
ただし、ボーナスは基本給や会社の業績、社会の状況によって上下します。今は基本給がそれほど高くなくても、将来的に成長が見込める会社であればゆくゆくは業績が伸び、基本給が上がり、高いボーナスが期待できるかもしれません。
業界の状況にアンテナを張り、将来性も考慮したうえで、転職先を選びましょう。
(3)業績連動型ボーナスを採用している会社
企業によってボーナスの仕組みは大きく異なります。基本給の何ヶ月分という固定的な算定方法よりも、業績連動型のボーナス制度を採用している企業の方が、成果次第で高いボーナスを獲得できる可能性があります。
営業職など目に見える成果を出しやすい職種の場合、業績連動型賞与や決算賞与の会社に転職することで、大幅に賞与が上がる可能性があります。
特に外資系企業や成長中のベンチャー企業では、会社や個人の業績に応じて大きく変動するインセンティブ制度を導入していることが多く、好業績時には年収の30〜50%がボーナスとして支給されるケースもあります。
ただし業績連動型の場合、会社の業績や自分の成果によっては、ボーナスが極端に低くなる可能性もあります。自身の能力と職場の成長性を見極めることが大切です。
(4)実力主義の会社
早くボーナスを上げたい場合やスキルに自信がある場合は、実力主義の会社がおすすめです。外資系企業やベンチャー企業など実力主義の会社であれば、年次・年齢に関係なく、成果次第で、どんどん昇格・昇給していき、ボーナスもアップします。
逆に年功序列の会社の場合は、希望するボーナス額に達するまで何年もかかるかもしれません。
ボーナスアップを目指して転職する場合は、転職エージェントに相談するのがおすすめです。希望に合った求人を紹介してくれるだけではなく、選考対策や入社時の条件交渉などのサポートを受けられます。条件交渉に成功すれば、より高額の賞与がもらえる可能性があります。
まとめ
ボーナスの額は、勤務先の業界・年齢・勤続年数・職種・役職・業績などによってさまざまです。厚生労働省の調査によると、1回あたりの賞与の平均額は約40万円です。
ボーナスの種類は大きく分けると、基本給連動型賞与・業績連動型賞与・決算賞与の3つがあります。
ボーナスを上げる方法としては、社内で成果を出す・会社の収益に直結する業務にシフトするなどがあります。
転職もボーナスを上げる効果的な方法のひとつです。ボーナス額が高い業界の会社・基本給が良い会社・業績連動型ボーナスを採用している会社・実力主義の会社は、ボーナスが高い傾向にあります。
転職する際は、転職エージェントを利用して、賞与の高い求人を紹介してもらう・給与交渉をしてもらうといったサポートを受けると効率的です。
特に賞与の多い職種の代表格であるMRへの転職は、医療業界専門のエージェントを利用すると、より質の高いサポートを受けられ、成功率が高まります。
ボーナスの種類は大きく分けると、基本給連動型賞与・業績連動型賞与・決算賞与の3つがあります。
ボーナスを上げる方法としては、社内で成果を出す・会社の収益に直結する業務にシフトするなどがあります。
転職もボーナスを上げる効果的な方法のひとつです。ボーナス額が高い業界の会社・基本給が良い会社・業績連動型ボーナスを採用している会社・実力主義の会社は、ボーナスが高い傾向にあります。
転職する際は、転職エージェントを利用して、賞与の高い求人を紹介してもらう・給与交渉をしてもらうといったサポートを受けると効率的です。
特に賞与の多い職種の代表格であるMRへの転職は、医療業界専門のエージェントを利用すると、より質の高いサポートを受けられ、成功率が高まります。
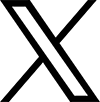
この記事が気に入った場合は
Xへポストをお願いします
