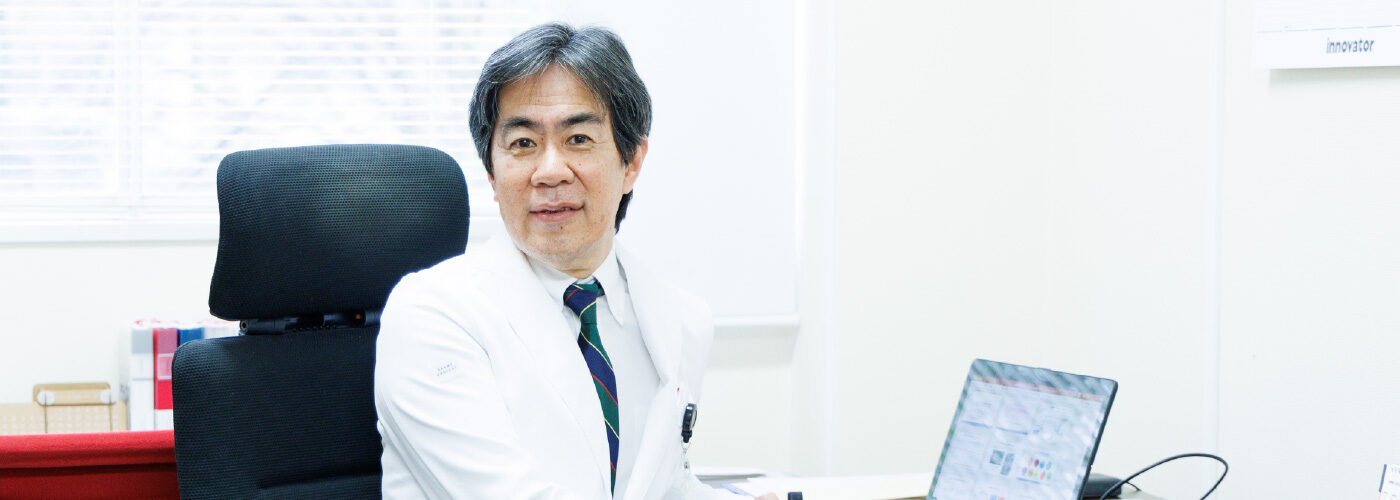富山大学の形成再建外科・美容外科の初代教授として、診療と研究に取り組む佐武教授。乳がん患者のQOLを向上させる乳房再建手術や性別適合手術、形成外科医の育成など、多方面で活躍している。形成外科医としてのキャリアと現在注力している取り組み、若者たちへのメッセージなどについて伺った。

キャリアにおける成功体験と失敗体験について伺ったところ「成功体験は、チャレンジしたこと全て。失敗体験は、チャレンジしないで後悔したこと全て」という答えが返ってきた。佐武教授のチャレンジの軌跡を振り返る。
医学生になった頃は心を治す医者、精神科医になりたいと思っていました。しかし実際に勉強してみると、当時、精神科では対症療法が中心で、心の病を完全に治すことが難しいことを知りました。人の心を治す医者になりたいけれど、精神科は自分には向かないんじゃないかと感じたんです。
転機は大学4年生の時、救命救急センターでの実習で火傷患者を担当したことです。精神疾患の影響で灯油をかぶり、火傷した患者さんの治療に携わりました。救命した後に、機能や見た目の改善、社会復帰の手助けをする領域があることを初めて知ったのです。当時はまだ形成外科自体があまり知られておらず、新しい診療科でした。外見を治すことによって患者さんの術後のQOLや生き方を改善できることを知り、自分のやるべき仕事だと思い、形成外科に進みました。
その後、埼玉県川口市の病院で8年間外科医として研鑽を積みました。そこでがん患者さんの治療に多く携わり、外科の基本を学びました。この経験が今の私の土台になっています。外科医として働く中で、形成外科へのニーズも感じていました。
2002年から横浜市立大学に移り、本格的に形成外科医としてのキャリアを歩み始めます。2003年に初めて乳房再建手術を執刀したところ、患者さんが非常に喜んで「先生はこれを生涯の仕事にしたらいい」と言ってくださったのです。その方がブログなどを通じて全国に情報を発信してくださり、多くの患者さんが横浜まで治療を受けに来るようになりました。
形成外科の治療は、結果が見た目ではっきりわかります。患者さんから厳しいご要望やご指摘をいただく機会も少なくありません。若い頃は、乳がんの患者さんは私よりも年上で、家族がいて社会で活躍している方が多かったです。単に胸を再建するだけでなく、その方のバックグラウンドや仕事なども聞きながら、最適な再建方法を一緒に考えてきました。プレッシャーも大きかったですが、形成外科医として大きく成長できました。患者さんは私にとって師匠であり人生の先生でもありますね。
その後、医師としてのキャリアの最後を、地元・富山県に恩返ししたいという思いから、2020年1月に富山大学に形成外科を新設する際に着任しました。富山大学にはそれまで形成外科がなく、文字通り何もない状態からのスタートでしたね。必要な人材を集め、信頼される体制を作り、県民に形成外科の役割を伝える活動から始めています。
着任後、富山大学附属病院は県内で最も乳がん患者さんの治療を行う施設となり、現在の富山県の乳房再建率は東京都に次いで全国第2位です。日本の乳房再建率は十数%と他の先進国と比べて低いので、再建手術を全国に広げる活動に取り組んでいます。
コンテンツは会員限定です。
続きをご覧になるには以下よりログインするか、会員登録をしてください。